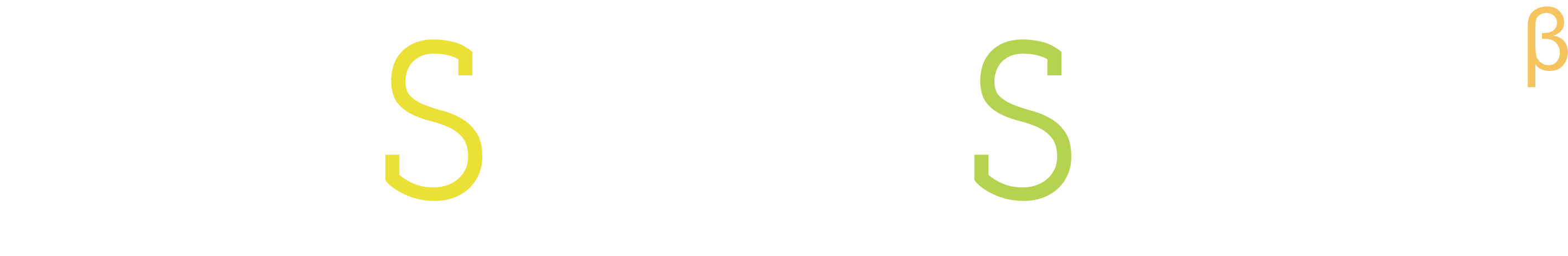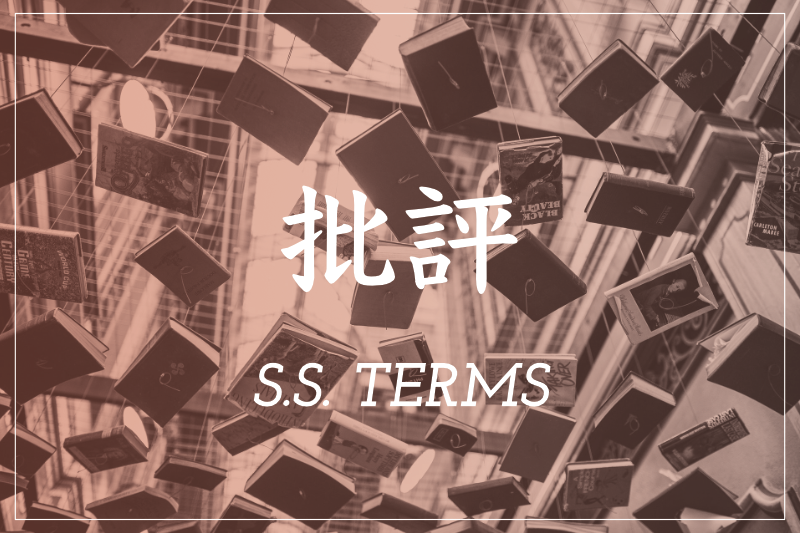「◯◯学なんてどうせ後付で付けられていくものなのだから学生のうちくらい、いろんな分野の考え方や問題意識を共有できるようにすればいいのになぁ」
そんなことを考えたことはありませんでしょうか?僕は嫌というほどこのことを考えて早3年くらいになります。
どもども、Share Study代表のとしちる(@ture_tiru)です。
Share Studyを勝手にひとりで立ち上げてから、勝手にインタビューをしたり、勝手に高校生や大学生に向けて学問を紹介したり、勝手に全国47都道府県を旅して「これまでを学び、これからの大学を考える」というイベントを開くなど、勝手なことをしてきました。
[kanren2 postid=”3466″]そして、またまた勝手に考えてしまいました。それが、「ADVENT CALENDAR(アドベントカレンダー)」です!
ADVENT CALENDARとは
12月1日から24日までクリスマスを待つまでに1日に1つ、穴が空けられるようになっているものをADVENT CALENDARと言います。Web上では、その風習に習い、12月1日から25日まで1日に1つ、みんなで記事を投稿していくというイベントをエンジニアの方々などが中心に行っています。
Share Studyでは「人と知のネットワーク化プロジェクト」として展開している「Share Studies」の取り組みと合わせて、Share Studyに関わる人々(スタッフ、メンバー)がそれぞれの学びや考えを共有するきっかけとなる場として、このADVENT CALENDARを開催致します。「Share Study」の運営の裏側をまとめる『裏Share Study』に「Share Studies」と「ADVENT CALENDAR」の内容についてまとめた記事を作成しております。詳しくは下記を参照ください。
ADVENT CALENDAR 2018の投稿記事一覧
- 宇宙の未来をみせるタイムマシン―国際リニアコライダーで探るダークマター
- オープンな監視社会とデータの軍事利用:中国人が歓迎する信用スコアシステム
- Share Studyとメタ若手ネットワーク―学術コミュニティーの調査・分析・接続・改善に向けて
- 筑波大学「哲つくば」の取り組みと成果―知的頭でっかちにならないために
- 筑波大学『雙峰論叢』の試み―文系不要論へのカウンターとしての挑戦
- ぼくとつくば②ー地域開発の中で混じり合う《つくば》
- 私と日本語教育学―「先生いなくなって、1人でできるもん!」を目指す
- 国際学と都市工学の異文化体験記―「まちづくり」とは何たるか
- 大学院生に朗報なacademist Fanclubとは?―academist PRIZE vol.3チャレンジャー参戦録
- 地域志向教育(アクティブ・ラーニング)を学生の立場から語る
- 文学部生き残り大作戦β:「である学問」から「する学問」へ
- 宗教の生きる現場ー「臨床」への宗教学の挑戦
- 学問の知と臨床・実践 —表層と本質という視点から—
- 私が生物言語学を研究する理由—人間本性探求—
- 「サイエンスコミュニケーションの重要性」とはー実践を通して考える二つの問題点
- あらゆる現象の「地図」を描く ―学術の教科書的分断からGoogle Map的統合へ―
- One Earth Guardiansになるために―総合的・多元的に農学を学ぶ意義と取り組み —
- 分野を越えたこれまでの取り組み―「若手研究者ネットワーク」の展開へ
- 赤の女王仮説に見る、生物の進化と現代社会の接点
- 地域と交わり、新たな教育の場を作る―長野県小布施町の取り組み
- 国際協力は偉いのかー活動を通して振り返る利己/利他の捉え方
- 学問としての翻訳研究とはなにか―関西大学 山田優教授へのインタビュー
- 国際教育開発のトレンド?―「住民参加型学校運営」の基本を押さえよう
- 元生物講師がまちづくり会社を学生起業し、生態系を学び考え実践し続けた8年間。
- 思想β 2018ー教養と視養:学術的探究と交流を紡ぐ概念に向けた試論
ADVENT CALENDARの開催背景や狙い
教養主義と出版文化
竹内洋(2003)『教養主義の没落 変わりゆくエリート学生文化』という本を読んだことはありますでしょうか?
この本では、旧制大学から新制大学へと移り変わる中、いわゆるエリート学生文化をその当時の社会状況などと合わせて分析している新書になります。今では新書というとかなり手頃に読めるものも増えてきましたが、この書籍は教育社会学の知見を踏まえてまとめられている書籍で情報量も多く、読み応えがあるものです。
今では「教養主義」というものが「何をいまさら」と思われてしまう概念かと思いますし、かくいう僕も、いわゆるかつての「教養主義」を復活させたいと思ってShare Studyを運営しているわけではありません。しかし、昨今、「大学の危機」が叫ばれて久しい状況が歴史的な地続きの中のことだと考えると、「なんでもあり」といった相対主義的なものに回収されてしまうことにはどうしても違和感を覚えてしまうのです。
『教養主義の没落』では、かつて「教養」として一定の権威や地位が成り立っていた状況を「アカデミズムとジャーナリズム」の相補的な関係性、「出版文化」として岩波書店をはじめとした出版社が築いていたことを指摘しています。しかし、今の現状はどうでしょうか?「Publish or Perish」どころか「Publish and Perish」ということばが用いられ、情報技術の発展の中で情報の価値はまたたく間に相対化され、マスメディアやソーシャルメディアなど、あらゆる媒体によって情報を受け取り、それだけでなく発信できるようになっています。
では、こうした現状の中で、「学ぶことの価値」、言うなれば「突き詰めることの価値」、「検討することの価値」はどのように担保することができるのでしょうか?
Share Studyは上記のような問題意識を抱く中で立ち上がった学術系のWebメディアというわけです。
これまでを学び、これからの大学を考えるACADEMIC CAMP
Share Studyを立ち上げたのは2016年9月、当時、「シェアリングエコノミー」などが流行っていた時期でした。その影響を受けつつ、単にシェアするだけでなく、それぞれの価値観や考え方がシェアされる中で「ゆらぎ」を味わい、「学問」という土台を引き継いで学びを深めることを意図して立ち上げたわけです。
しかし、「失われた20年」と叫ばれ、2011年の東日本大震災などの影響からさらに強まった「地方創生」、さらにその背景の根っこにある「人口減少」を見据えた社会制度を整えることを考えることなしに、「大学」や「学問」は成り立たないと考えていました。
そこで、僕が所属するなんだかんだで日本の大学トップテンである「筑波大学」、人気度ランキングで毎回最下位になる茨城県だけどもなんだかんだで「関東」という中心に位置する場所を飛び出して、47都道府県をこの目で見聞きし味わい、それでいてこれからを考えることを志向する人が集まる『ACADEMIC CAMP』を開催したのです。
イベントを終えての、詳しい現状認識については下記もご覧ください。
ACADEMIC CAMP以降の現状認識
集まった場では熱気の伴ったコミュニケーションが交わされた側面もあるのですが、やはり地理的な距離感や問題意識の共有、知識情報思考の熟成がそれぞれのレベルで異なっていたこともあり(これは当然なのですが)、思うように学び合いを深められなかった側面がありました。
当然、昨今の現状に対する問題意識という危機感も人によりまちまちです。
さらに、現在、マスメディアだけでなく、さまざまなWebメディアが登場してきましたが、それぞれの立場や価値観を一定程度尊重しつつ「学び合いを深める」というよりも、「自分の好きなものを見る」ということに回収されがちになってしまう、ということに気づいてきました。
確かにソーシャルメディアや仮想通貨やブロックチェーン技術を用いた、個々人のキャラクターや能力を尊重することに特化させていくことも大事です。しかし、当然、それぞれの「自由」はそれを主張しあって対立します。ですから、単に自己主張するだけでなく、どのように折り合いを付けていけるかという、「(広義の)政治」を抜きにしては語れないのですが、このソーシャルメディア時代には捨象されてしまいがちです。
いや、おそらく「捨象」というよりも、誰しもが発受信をする中で「可視化」されるようになったというのが正確なのかもしれません。少なくとも、TwitterやFacebookをはじめとした媒体は議論に向かず、ということは学び合いも熟成されるにくいと、より強く考えるようになりました。
ADVENT CALENDARの狙い―編集する発受信という経験
リアルに異なる他者と出会っても、関係性づくりにも時間がかかるし、親密性が下手に強まることもまた辛い、かといって個々の自由が尊重されるためにもめんどくさいコミュニケーションを取ることが肝心だけども、それも避けられてしまう。
であれば、どうするかというのがShare Studyを運営する僕の今現在の問題意識です。
いわゆる単に「消費」されないで、考えること、学ぶことを深めるためにはもう少しゆっくりと時間をかけて、それぞれのまなざしを共有していく土台を作る必要があるという考えが強くなったここ最近。そこで、登場するのがADVENT CALENDARです。
毎年、一年間を振り返ることができる12月の時期であること、異なる他者がちょうどいい距離感で視点や学びを共有できるものとして、一年に一度、というのも適切ではないかと思うのです。
また、「記事を執筆する」という経験は、単にレポートや論文を書くこととは異なり、「読者」を意識して書くという経験をすることになります。教養主義の文化が出版社を通じて読者との関係性を作っていたように、これからの「大学」や「学問」の意義や価値をやり取りするためにも、「編集する」ということを経験することは重要でしょう。
このような実践は「サイエンスコミュニケーション」と部分的に呼ばれてきました。Share Studyでは、サイエンスコミュニケーションの考えを引き継ぎつつ、学生や若手教職員をはじめとしたさまざまな立場の人がやり取りを交わし、他者の声を聞き、また己の声を発することを為していきたいと考えています。
「人と知のネットワーク化プロジェクト」と称した「Share Studies」も「ADVENT CALENDAR」も、上記のような問題意識や手法を具体化させたものです。今後、より洗練された仕組みを練り上げていきたいと考えています。
現在、「ACADEMIC CAMP」から端を発しつつ(このイベントだけではありませんが)、構築されつつある「メタ若手の会(仮)」という取り組みがあります。2018年度は、一定の問題意識を共有した人々で叩き上げをしつつ、今後、より「学び合いの文化を熟成する」ことに寄与する活動を展開していきます。
以上、長くなりましたが、これが「Share Studies」や「ADVENT CALENDAR」の実施を行う背景です。
「まじめにふまじめに、ふまじめにまじめに」、ことばを交わしていきましょう!