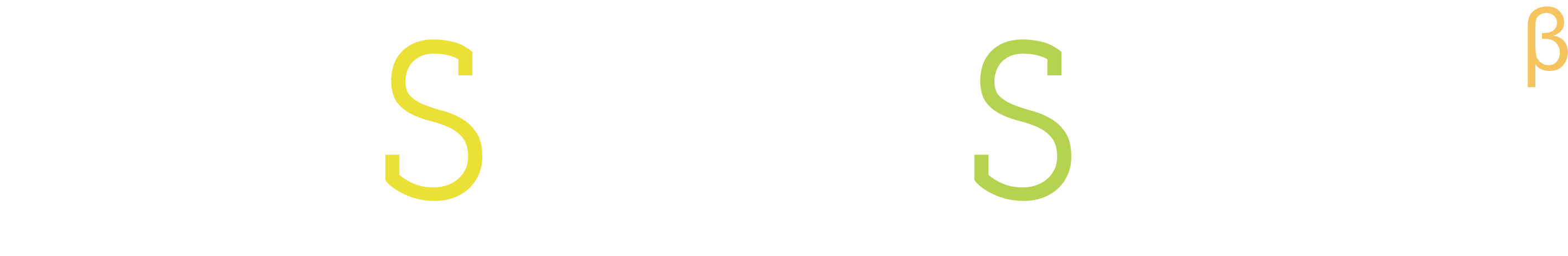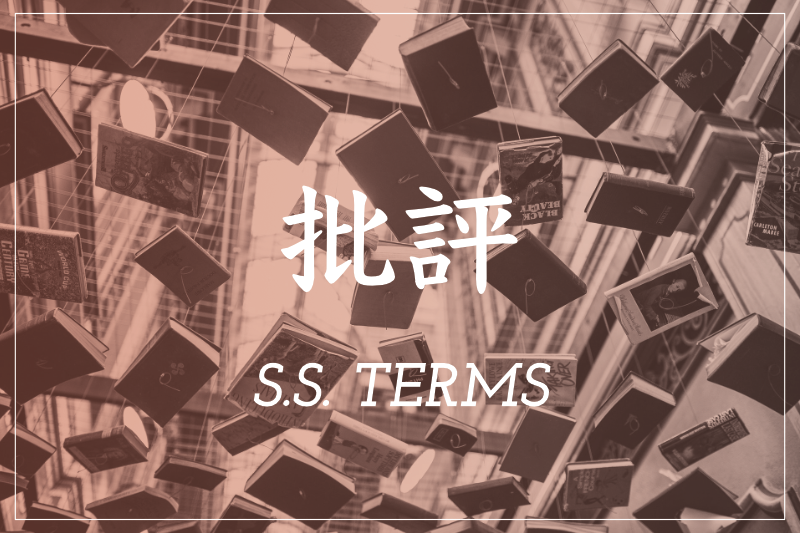専門的な知識や研究内容ではなく、広く学びに携わる・携わった「人」に焦点を当て、どのような経緯を経て今に至るかといったことを探る記事カテゴリー、それが「アカデミックインタビュー」!
第10回は、九州大学次世代型大学教育開発センター特任助教として勤務なさっている小林良彦さんに
- 研究分野の原子核物理
- サイエンスコミュニケーション活動
- 研究・活動に至った経緯・背景
などについてお聞きしていきます。
Profile

小林良彦さん
専門分野:原子核物理学/サイエンスコミュニケーション
趣味:読書、サイエンスカフェ、生き物観察
ホームページ:小林良彦のウェブサイト
ブログ:原子の核心にせまる
原子核物理学とは何か
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]こんにちは!新潟大学で研究に従事しつつもサイエンスコミュニケーション活動も積極的に行い、現在は九州大学次世代型大学教育開発センター特任助教になられた小林良彦さんにお話をお聞きしていきます。本日はよろしくお願い致します![/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/07/9_icon_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”r icon_red”]こんにちは!いやー、僕なんかでよろしければぜひお願いします![/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]まずは小林さんの専攻である原子核物理について、簡単に教えてもらえますでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/07/9_icon_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”r icon_red”]原子核物理では、超ミクロな世界である原子の中にある「陽子」や「中性子」の間に働く「強い相互作用」などについて探る学問分野です。原子核の核構造や核分裂などを扱うのですが、僕が専門としているのは原子核物理の中でも原子核構造論というものなんです。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]なるほど、人によってはあまり聞き慣れない言葉が早速並んでいますね。以下の引用を見てみてください。すべての物質は分子の集りから成る。さらに,分子は化学結合によって結ばれた原子から成る。個々の原子は電子と原子核から構成される。(中略)陽子と中性子はどちらも小さな粒子であるが,これらはクォークと呼ばれるさらに小さな粒子により構成されている。
「物質>分子>原子>原子核・電子>陽子・中性子>クォーク(素粒子)」というように物質は分解していくことができるんです。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/07/9_icon_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”r icon_red”]そうなんです!原子核構造論で何をやっているかというと、原子核の性質を理論的に探るということをやっています。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]あくまで「理論的に」なんですね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/07/9_icon_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”r icon_red”]はい、実験はまた別の専門領域としてあります。これまでは紙とペン、今ではコンピューターを用いて原子核の構造を探っています。超ミクロな世界について取り扱っているので、量子力学を用いた研究をしていますね。[/voice]
研究に携わるようになった経緯
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]小林さんはどのようにして研究者の道へと歩んでいったんでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/07/9_icon_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”r icon_red”]僕、もともとはですね、昆虫学者になりたかったんですよ。『ファーブル昆虫記』を読んでいた影響がありまして。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]あっ、そうだったんですか!確かに、時々SNSに生物の写真あげてますもんね(笑)[/voice]
小林さんがSNSに投稿した砂を食べるカニ
サイエンスコミュニケーションとの出会い
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]小林さんは研究だけでなく、サイエンスコミュニケーション活動も活発に行っていますよね。サイエンスコミュニケーションに携わるようになったのはどのような経緯があったんでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/07/9_icon_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”r icon_red”]実は僕、学部生の頃にもほとんどサイエンスコミュニケーションのことを知らなかったんです。外部から来た先生にたまたま教えてもらったことがきっかけで、修士の1年生になってから始めてサイエンスカフェに参加しました。さらにそこで、「サイエンスカフェにいがたの懇親会に来てみないか?」と誘われ、気づいたらスタッフになっていたというのがもろもろの経緯になりますね。[/voice] [aside type=”normal”]サイエンスカフェ:小規模の場でサイエンスにまつわるさまざまな話題をサイエンスコミュニュケーターである研究者や市民が一緒に対話する、学び合うための場。[/aside] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]なるほど、人との縁がつながってサイエンスコミュニケーションの道に歩んでいかれたんですね。新潟大学でのサイエンスコミュニケーション活動―新大Witsと学び合いカフェに携わってきたとお聞きしました。どのような活動だったのでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/07/9_icon_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”r icon_red”]新大Witsは新潟大学公認の活動団体で、大学院生が中高生に向けて出張講義などをしています。修士・博士課程在籍時の4年間活動に携わっていました。そこには、科学を研究する人ばかりでなく、哲学を専攻している人だったりさまざまな人と関わる機会がありましたね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]異分野の方々と触れ合って、何か変化はあったりしたのでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/07/9_icon_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”r icon_red”]特に哲学が好きになったんです。根底にあるものをぶち壊していくのは面白いですね。本屋を見る目も変わって、今まで読んだことのない本にも手を出すようになっていきました。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]もしかして、その経験が分野を問わずに活動していた『学び合いカフェ』につながっていったのでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/07/9_icon_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”r icon_red”]そうなんです!新大Witsで出会ったメンバーを中心に作っていったんですが言い出しっぺは僕でした。大学ではなく院生が主体となって、主に学内の大学生や一般向けに企画を行っていったのが『学び合いカフェ』でした。[/voice]原子核物理を専門とする者にとってのサイエンスコミュニケーション
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]サイエンスコミュニケーションを行っている方って比較的、生物学を学んでいる方が多い印象があるんですよ。小林さんの専門は原子核物理学ということですが、その分野もサイエンスコミュニケーションをしていく上ですごく大事な分野のように思います。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/07/9_icon_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”r icon_red”]そうですね、僕は楽しさとか魅力を伝えるだけでなく、危険なものを含めて伝えられるサイエンスコミュニケーターとして活動したいなって思っているんです。はじめてサイエンスコミュニケーションに魅せられた時にある先生からアドバイスされたのが、「しっかりと自分の専門分野を確立した方がいいよ。」でした。特に原子力にも関わるのがまさに僕の分野であり、専門性が求められるところだと思っていますね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]確かに、これまでの科学史などを振り返ってみると、科学技術がもたらした影響というのはすさまじいものがありますよね…[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/07/9_icon_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”r icon_red”]歴史を少しでも勉強すれば、原爆の発明など、必ずしも楽しいことばかりではないんですよね。これからのあり方を考えるためにも、一人の核物理学者としてサイエンスコミュニケーションできるようになりたいです。[/voice]最後に一言
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]これから小林さんが目指す研究者像というのはあるんでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/07/9_icon_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”r icon_red”]フクロウみたいな科学者になりたいですね。町外れにいて、聞きたいことがあれば話しにいける研究者に。いつもは疲れてしまうからちょっとでいいんです(笑)教えるのではなく、対話をしていきたいですね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]これからサイエンスコミュニケーション活動をしていきたいという若者に向けたアドバイスはありますか?かつて小林さんがアドバイスされたように、もし今小林さんがその立場ならなんとおっしゃるんでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/07/9_icon_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”r icon_red”]僕もまだまだですが、若者にとって、サイエンスコミュニケーションをする上での専門性のなさや内容を取捨選択する上でのバランスの難しさというものはあると思うんです。だけど、そんな若者だからこそ「分からない」ということを素直に言いやすいわけですよね。だから、「サイエンスコミュニケーションは”若い”からこそできる!」と敢えて言いたいですね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]…「サイエンスコミュニケーションは”若い”からこそできる!」、今の僕にも非常に響く言葉です…本日はありがとうございました![/voice]おすすめの本
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/07/9_icon_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l icon_yellow big”]『元素はどうしてできたのか』では元素と原子核の「いろは」から最先端の原子核物理研究を学ぶことができます。『量子革命』は量子力学を築いた物理学者たちの息吹に触れることができる本です。[/voice]インタビューを終えて
純粋な「知りたい!」という好奇心と、純粋な「伝えたい!」という好奇心を合わせ持ったのが小林良彦さんなのだなと思った取材。
過度に「伝えなきゃいけない!」でもなく、過度に「これが正しいあり方なんだ!」と主張するのでもない。
そうではなく、「こんな面白いことがあるんですよ。」と、「これはよく考える必要があるんです。」と語り、対話する姿勢を崩さない小林さんのあり方に学ぶことは多いのではないか?
そう思ったインタビューでした。
最後の「若いからこそできるサイエンスコミュニケーション!」を胸に、Share Studyの活動にも邁進していきたい、そう改めて思わされたインタビュー経験でした。