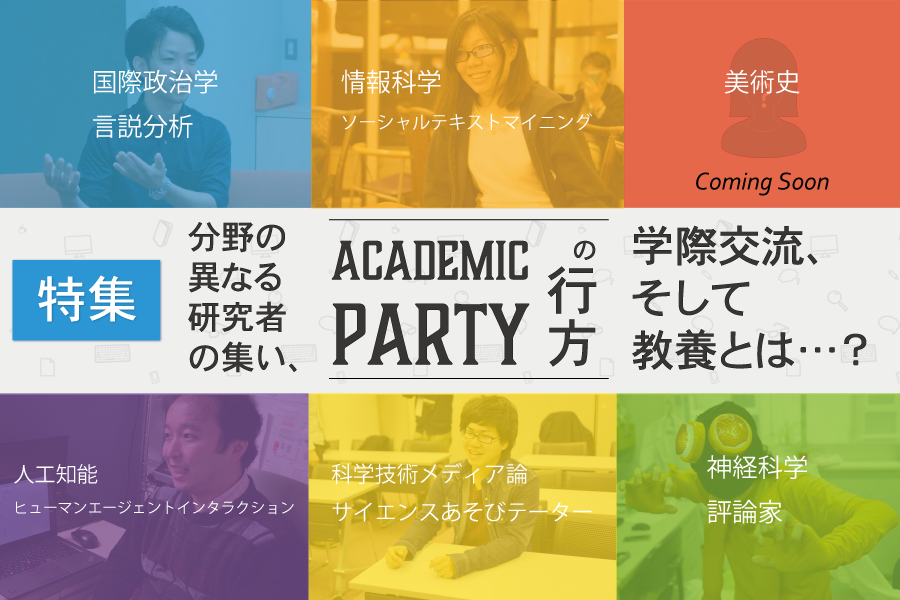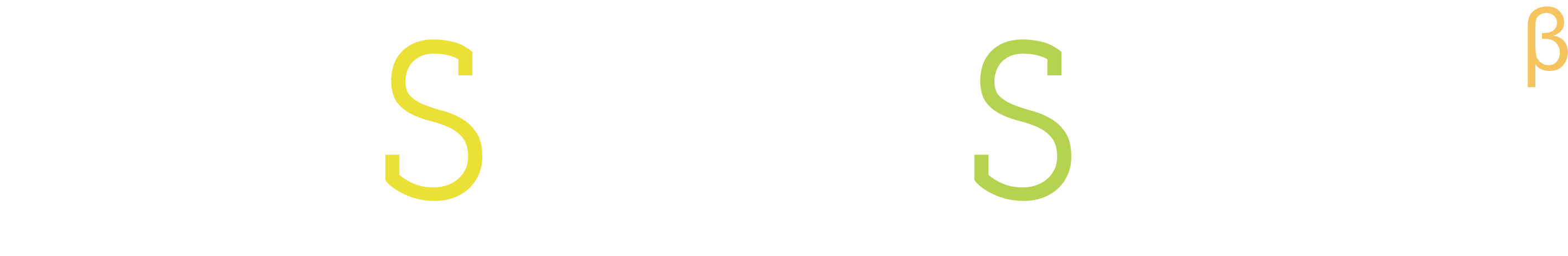専門的な知識や研究内容ではなく、広く学びに携わる・携わった「人」に焦点を当て、どのような経緯を経て今に至るかといったことを探る記事カテゴリー、それが「アカデミックインタビュー」!
第5回は、博士課程にて美術史の研究を行っているH.Sさんに
- 研究分野の美術史
- 主要研究である日本のプリミティヴィズム
- 研究に至った経緯・背景
などについてお聞きしていきます。
Profile

H.Sさん
キーワード:20世紀美術、プリミティヴィズム、日本の近代美術と「原始美術」の関係性」
好きなこと:美術館に行くこと、おいしいものを食べること、友達とおしゃべりすること。
美術史―19世紀植民地主義の影響を受け登場したプリミティズム
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]本日はよろしくお願い致します。H.Sさんは美術史を主な分野として研究なさっていると聞きます。具体的にはどのような研究をなさっているのでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/01/H.S.png” name=”H.S” type=”r icon_red”]私は美術史の中でもプリミティヴィズムというものに焦点を当てた研究をしています。プリミティヴィズムは20世紀前半の西欧近代美術において流行したものでした。19世紀の植民地主義の影響を受けて出てきた芸術概念なんです。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]プリミティヴィズムですか。初耳です!植民地主義の影響とはどのようなものだったのでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/01/H.S.png” name=”H.S” type=”r icon_red”]植民地からヨーロッパに物がたくさん運ばれてきて、経済的なつながりだけじゃなく文化的なつながりが西洋と諸外国に現れるようになったんですね。パリの芸術家を中心として、異文化への興味が引き立てられていったときに、西洋のアカデミックな美とは異なるものとして注目を浴びていったんです。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]なるほど、これまで経済的なつながりとして酷使していた人々の持つ文化が新たな美として注目されたのがプリミティヴィズムなんですね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/01/H.S.png” name=”H.S” type=”r icon_red”]そうですね。ただ前面に出る芸術概念としてはキュビスムやフォーヴィスムがあって、プリミティヴィズムは裏の立役者としてあった考え方なんですね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]そうだったんですね!通りであまり聞かないわけだ。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/01/H.S.png” name=”H.S” type=”r icon_red”]交流と言うと聞こえはいいけど、西洋中心主義的な一方方向の眼差しでもあるわけです。そこが気になるところなんですけど。で、私はプリミティヴィズムの日本バージョンを研究してます。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]あっ、日本バージョンなんですね![/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/01/H.S.png” name=”H.S” type=”r icon_red”]そうなんです。いつも前置きが長くなってしまうんですけど(笑)[/voice]20世紀日本におけるプリミティズムとは
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]日本の場合はどのようにプリミティヴィズムを捉えることができるんでしょうか?ここまでの話だと西洋の話が中心にあったと思うのですが。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/01/H.S.png” name=”H.S” type=”r icon_red”]日本は地理・経済・文化的に、西洋と植民地地域の中間に位置づけられることが多く、それを当時の日本人たちも自覚しているところがあるんですね。そういう意味で、プリミティヴィズムについても第三の視点が出てくるわけです。ヨーロッパでは西洋と植民地という二項対立として捉えられるのですが、日本の場合は中間の立ち位置を取るので、第三者の視点も絡んでくるんですね。これが日本におけるプリミティヴィズムの特徴です。 [/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]日本が地理的にだけじゃなく、さまざまな点で中間的な立ち位置にいるのは感覚的にも分かる気がしますね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/01/H.S.png” name=”H.S” type=”r icon_red”]日本人はヨーロッパ人に対して文化的に高尚なものを彼らはやっているという認識がどこかある一方で、アジアとか南洋、日本国内の地方の人たちを、西洋とは異なり高尚ではないと見るところがあります。。
ですが、これらの文明化から「遅れた」地域には自分たちが失ったものがあって、それに憧れたり懐かしがったりする気持ちも抱くことがあります。こうした気持ちがプリミティヴィズムの中にあるんですね。一見すると問題なさそうなものの中に「文明」からの一方向的な眼差しが潜んでいるのが、プリミティヴィズムのわかりにくいところかもしれません。 [/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]なるほど。二項対立として捉えられるほど単純なことってほとんどないんじゃないかってことが勉強していくと見えてきますよね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/01/H.S.png” name=”H.S” type=”r icon_red”]はい、物事は本当に単純じゃないことが多いですよね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]現代との関連性も研究の射程には入れているんでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/01/H.S.png” name=”H.S” type=”r icon_red”]論文の射程が1910年代から1970年代までなので入れてはないんですが、気になってますねぇ。例えば、美術館や博物館の問題としては、かつての植民地から持ってきた作品の返還が要求されることもあります。また、異文化の表象を誰がどのようにするのかという点も、20世紀的なプリミティヴィズムから続く一つの論点だと思います。これらの問題に対して、海外や日本の美術館・博物館がどのようなリアクションをしているのかについても興味があります。[/voice]
どのようにして美術史の研究をするようになったのか
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]なるほど。単純に美術史の研究をしているのではなく、現代における諸問題にもつながる研究テーマになるんですね!では、このような美術史の研究にどのようにしてのめり込んでいったのでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/01/H.S.png” name=”H.S” type=”r icon_red”]最初のきっかけは、大学生の頃にヤング・アメリカンズのお手伝いにボランティアとして参加したことでした。ヤング・アメリカンズはアメリカの同世代の大学生と一緒に、小中学生に向けて英語で音楽のワークショップをするというものなんです。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]ヤング・アメリカンズの活動と美術史の研究をするに至ることにはどういった関係があったのでしょう?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/01/H.S.png” name=”H.S” type=”r icon_red”]ヤング・アメリカンズでのボランティア活動を通して「芸術には人を変える力があるんだな」って気づいたんです。彼らはプロフェッショナルではないけど、何か持ってるものがあるなと。アーティストたちがつくる「アート」と呼ばれるものとそうでないものを区別をしているものってなんだろうって考えるようになっていったのが美術に興味を持っていった経緯なんです。[/voice]
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]「アートと言わせているものとは何か」という問いがヤング・アメリカンズの経験を通して芽生えたんですね。[/voice]
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/01/H.S.png” name=”H.S” type=”r icon_red”]活動をする中で、アメリカ人と帰国子女の子たちは察知できない日本の文化的なものに、自分は敏感に察知できるなって気付いていったんです。そこから、自分の得意分野として「日本美術」をやろうと思っていきました。[/voice]
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]大学から修士に進学するにあたってはどうだったのでしょうか?[/voice]
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/01/H.S.png” name=”H.S” type=”r icon_red”]大学のときの卒論は美術館の鑑賞教育をやってたんですね。専門家ではなくて一般の方がどのように芸術を鑑賞していくのかが気になっていて。最初は学芸員になりたいと思ったので、修士号を持ってた方が転職に効くと先輩から聞いて大学院進学を考えはじめました。大学では主にリベラルアーツを学んでた関係で、自分の専門性を高めたいと思うようになったこともあって修士に進みました。[/voice]
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]なるほど。博士に進むにあたってはどうだったのでしょう?[/voice]
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/01/H.S.png” name=”H.S” type=”r icon_red”]博士に進んだのは研究が楽しくなっちゃったからなんですよ(笑)修士の頃にイサム・ノグチという一人の作家に焦点を当てた研究をしたのですが、その他もろもろにつながっていく波及力の高さにすごく魅力を感じたんです。 [/voice]
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]単純に研究が面白くなっちゃったってのはいいですね(笑) 修論で取り上げたイサム・ノグチさんとプリミティヴィズムにはどのような関係があったのでしょうか?[/voice]
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/01/H.S.png” name=”H.S” type=”r icon_red”]イサム・ノグチはアメリカ人なのですが、美術的な観点から見ると日本・アメリカ・ヨーロッパという三者間を行ったり来たりするような美術的アイデンティティを持っていました。彼にとってはアフリカとかオセアニアではなく、日本でプリミティブな原始体験をしていったことが世界におけるプリミティズムと関連して見えてくるのが面白かったんです。 [/voice]
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]なるほど、イサム・ノグチさんという一人の方に日本ならではのプリミティヴィズムが垣間見れたんですね!
ところで先ほどは、学芸員になりたかったとの話がありましたが、学芸員になるには無理に博士に進まなくてもと思うのですが…[/voice]
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/01/H.S.png” name=”H.S” type=”r icon_red”]そうなんですよね(笑)研究するのが楽しかったですし、プリミティヴィズムの研究をもっと幅を広げてやってみたくなっちゃったんですよ。大学に残ってれば、研究もする傍らで、美術イベントを開いたりとか、授業を持てれば鑑賞教育みたいなこともできるじゃないですか。教育にも関心があったので、私にとっては研究職にすごく魅力を感じていったんです。[/voice]
高校生や大学生といった読者への一言
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]今回は美術史に関するさまざまな話やH.Sさんが研究にのめり込んでいった背景をお聞きすることができてとても面白かったです!最後に高校生や大学生といった読者に向けて一言あればお願いします。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/01/H.S.png” name=”H.S” type=”r icon_red”]本当に自分の好きなことやったらいいと思います。私は自分が楽しいと思えたこと、心地いいと思えたことしか続けてないし、続けられないと思うので。どこの時点で、自分にとってベストなのか、ベターな心地よさを感じられるのかを知ることが、人生を生き抜いていく上で大事だなぁと思います。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]そうですよね。自分にとって何が良いことなのか早いうちに察知できるとだいぶ楽ですよね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/01/H.S.png” name=”H.S” type=”r icon_red”]若いうちにいろいろなことを経験する中で見えてくるんじゃないかなと思います。仮に大学で見つからなくても、就職した先で見つけられることもあるだろうし。ポジティブにいって貰えればと思います。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2016/12/interview_icon.png” type=”l”]いやぁ、ごもっともだと思います。今日はありがとうございました![/voice]
おすすめの本&美術館
おすすめ本
[colwrap] [col2]
[/col2] [col2]
 [/col2] [/colwrap]
[/col2] [/colwrap]
おすすめの美術館
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/01/H.S.png” type=”l big icon_yellow”]今回、本だけじゃなくおすすめの美術館も一緒に紹介させて頂きました。よろしければぜひ足を運んでみてください。[/voice]インタビューを終えて
大学生活で携わったボランティア経験を通じて、研究にのめり込んでいったH.Sさん。
そんな彼女の背景には、「人にアートと言わせているものとは何か」という問いがありました。それは、勉強をし続けたから見えてきたのではなく、実生活の中で経験を通して芽生えた問いでした。
まさにこれこそ、学問が「問い」からはじまる好例なのではないかと思います。
ただ研究するだけでなく、積極的に外にも出ていく背景には「自分が本当に居心地のいいもの、楽しいと思えるもの」をやるというH.Sさんの姿勢があったのでした。研究者の中には「楽しいからやる」という純粋な気持ちを持つ人も多くいるように思います。そんな自ら「楽しむ」姿勢を見習いたいと思うのでした。