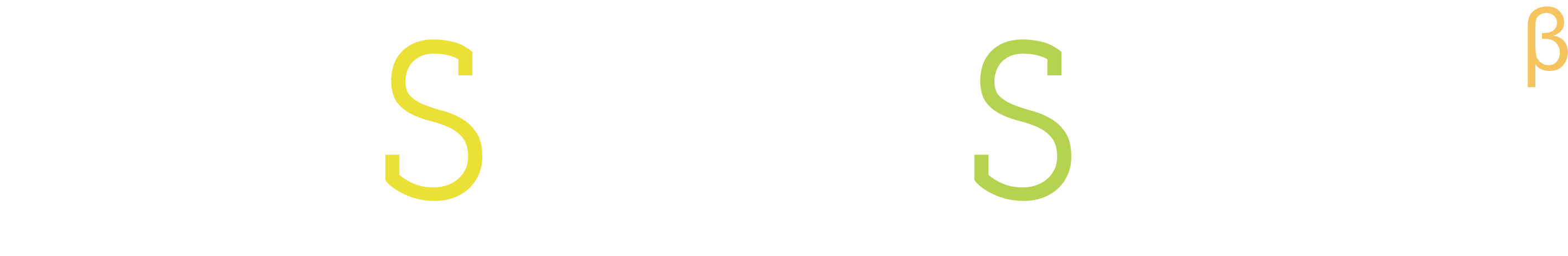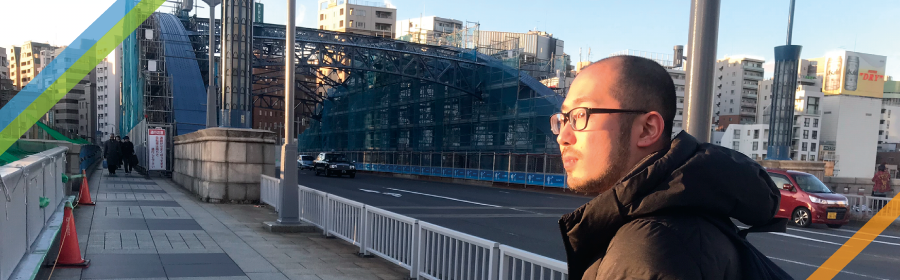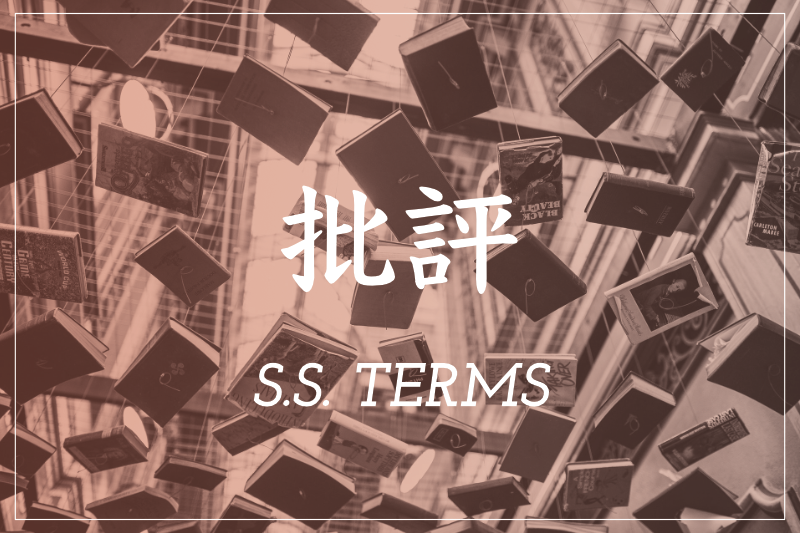専門的な知識や研究内容ではなく、広く学びに携わる・携わった「人」に焦点を当て、どのような経緯を経て今に至るかといったことを探る記事カテゴリー、それが「アカデミックインタビュー」!
「学習は好きで、教育は嫌い」
「批評にも文学にも運動にもノンフィクションにもジャーナリズムにもリアリティを持つことが難しい」
第12回のアカデミックインタビューに登場するのは、批評紙『Rhetorica』の発行や“教育”型下宿の経営、さらには島根県立大学にて大学の広報業務を行っている瀬下翔太さん。Twitterを介して知り合ったとしちるが瀬下さんの活動のこれまでとこれからについてお話をうかがいます。
- 大学では討論型世論調査の研究プロジェクトに関わるも、徐々に批評活動がメインに。きっかけは先生から「お前のやってることは違うよ」と言われたこと。
- 「デザイン×批評」の視点で編集されているのが『Rhetorica』。
- 地域における批評の可能性が具現化したものとして『新復興論』と『空をゆく巨人』を推薦。ここに文化と運動の接点となる「ローカルアクティビズム」がある。

1991年生まれ。編集者。埼玉県生。島根県在住。NPO法人bootopia代表理事。批評とメディアのプロジェクト・Rhetoricaをやったり、島根県で高校生向けの下宿屋を運営したりしています。最近では、大学の広報誌を学生と一緒につくったり、ユーザー参加型のメディアをつくったりも。
文化運動―新しい「文化的なもの」をつくる活動

こんにちは! 島根県津和野町で高校生の“教育”型下宿活動を行いつつ、批評誌『Rhetorica』の製作や島根県立大学にて嘱託員として大学の広報誌の編集長も務めるなど、多岐にわたる活動を行う瀬下さんにお話をうかがっていきます。よろしくお願いします!
はいよろしくです。

僕がはじめて瀬下さんと接触したのはTwitterを介してでした。最初の印象は「批評誌を作ってる人ということは、いわゆる批評家なのかな?」でした。ですが、『POSSE vol.38』におけるリレー連載((「それぞれの町で リレー連載第3回 瀬下翔太×石井雅巳 下宿と津和野 自律した知的探究と親密さについて」POSSE vol.38 P126-133))を読むと、高校生の頃にはゼロ年代批評に触れ、大学に進学したもののアカデミックキャピタリズムをはじめとした大学の変革や批評ブームが去る中で、津和野町に移住し、教育型下宿をはじめた経緯が描かれていますよね。
ゼロ年代批評:コンテンツやウェブサービスなど広い意味での大衆文化と、社会や技術での関係を対象とした思考を展開する、2000年代に現れてきた新しい批評の潮流1。
アカデミックキャピタリズム:1980年代以降に加速した「大学資本主義」を指す用語。日本においては2004年の国立大学法人化をはじめとした政治的背景を指して用いられる用語。
『Rhetorica』は批評誌だと思ってますが、自分で批評を書くことはほぼないし、批評家ではないっすね。POSSEにも書きましたが、NPOの運営や雑誌制作を通じて小さい「文化運動」のようなことをやってる気持ちで活動しています。

文化運動は、哲学・思想、文芸、はては科学に関する文化的な活動を通じて、既存のものにはない、新しい価値観をはじめとした文化を作っていく活動ですよね。批評誌『Rhetorica』は瀬下さんの取組の中でも際立ったものだと思います。『Rhetorica』とはどんな雑誌なんでしょうか?
『Rhetorica』―デザイン×批評
『Rhetorica』は2012年の大学2年生のときに仲間と一緒につくり始めた雑誌で、隔年で発行してる。『Rhetorica #04』が最新の号で2018年12月に出版したんだけど、今回はわりと売れ行きが良くて、もう完売したから、そのうち増刷するよ。


表紙の鯨がめちゃめちゃかっこよく、哲学や文芸批評に携わっていなくても思わず目に入ってしまうデザインだと思いました。特集「つくることと生活・集団・都市の関係」ということでしたね。つまり、「つくり続けるために必要な条件」だと。
ありがとう。創刊号である「Rhetorica #01」の特集は「つくり続ける生き方をつくる」だったんで、こういうテーマは二回目になる。いまは編集部の多くが学生ではなくなっているし、ゼロ年代批評のブームもないから、創刊号の頃とは公私ともに状況が違っている。「つくり続けるために必要な条件」を探ると言っているのは、状況が変化した今でも、自分(たち)にはそれが見えてこないっていうもどかしさがあるから、どうしたらいいのか考えたいなと。真っ暗な表紙にその「怒り」が込められていると思う。

「#04」で繰り返し登場するのがマーク・フィッシャーの『資本主義リアリズム』でした。瀬下さんが大学を卒業後、就職をしたにも関わらず、津和野へと向かうようになったのも、大学や批評を取り巻く資本主義的論理や社会的風潮への忌避感だったかと思います。瀬下さんが今の活動に至るまでの経緯をお話いただけますか?
資本主義リアリズム:「資本主義が唯一の存続可能な政治・経済制度であるのみならず、今やそれに対する論理一貫した代替物を想像することすら不可能だ、という意識が蔓延した状態[マーク・フィッシャー, 2018]」を指す。
大学入学前と大学入学後
大学入学前―ネットに育てられたゼロ年代前半

中高生の頃は深夜ラジオとインターネットしかやってなかったなあ。TBSラジオのJUNKで「伊集院光の深夜の馬鹿力」や「爆笑問題カーボーイ」、「文化系トークラジオ Life」、文化放送で「田村ゆかりのいたずら黒うさぎ」あたりを聴いてました。ラジオに出てくる知らない固有名詞を検索して、2ちゃんねるやはてなダイアリーのコミュニティを知った。
『Rhetorica』の活動では仲間を募って8年間も冊子制作を中心とした活動をしていますが、その中でも「地域」や「教育」をテーマに家族的な友人関係を作っている様子を見ると、今の活動との違いを感じました。
たしかに「インターネット」から「地域」へってまとめると、ちょっと不思議な感じがするか。でも『Rhetorica』の仲間も島根県への移住を誘ってくれた先輩も、みんな知り合ったきっかけはTwitterだし、自分では地続きな感じがする。自分はインターネットに育てられたという気持ちが非常に強い。教育について言えば、自分自身が興味のあることでないと熱入らないし、興味持ったら勝手に本を読むっていう「教育は嫌いで、学習は好き」なタイプだったので、いまそういう仕事に従事してることに対して複雑な気分がある。いまの津和野町での活動を「“教育”型下宿」と呼んでいるのも、ほかに言葉が思いつかないので暫定的にっていうかね。「学習支援型下宿」でもいいんだけど、なんか違う印象になっちゃうし。

なるほど、確かに僕もやりたいことがたくさんあるので、それを阻害される「押し付けられた教育」は好きではないのでよく分かります。
大学入学後―討論型世論調査から批評誌の作成へ

ネットを介して広く文化的なものに浸っていたところからどのように大学に入学していったのでしょうか?
ゼロ年代は新書ブームだったこともあって、高校生になると人文社会系の新書をいろいろ読んでた。だから、自分は文学部に入るんじゃないかとなんとなく思ってたんだけど、入試で落ちたので、受かったところに入った感じっす。

「ゼロ年代」と呼ばれるタイミングではこれまでの伝統的な文学ではなく、サブカルの中に批評性を見出すものがとても多かったと耳にします。特に当時活躍して、今も一線を張っているのが東浩紀さんかと思いますが、瀬下さんもかなり影響を受けてたそうですね。
うん。高校生の頃に「東浩紀のゼロアカ道場」という企画が始まって、批評同人誌をつくって文学フリマで売ったり、ネット上で批評家が喋っている様子を中継したり、東さんを中心にムーブメント感があった。はてな上でのいろいろな議論も含めて、わけわかんないけど楽しそうだったからずっとそれを追っていたら浪人した。大学に入ってもいないのに、大学院に行って文学理論とか勉強するんだと思ってた記憶がある。

結果的に瀬下さんは大学院に進学しなかったわけですが、大学入学後にどんな変化があったのでしょうか?
仲間と『Rhetorica』をつくったことと、大学で取り組んだ「討論型世論調査」の経験が大きいかな。『Rhetorica』は、いまから振り返ればさっき話した批評系の同人誌のブームがあったからできているんだけど、当時の自分たちとしてはそういうものと違うと思っていた。テーマも「デザイン」が中心だったので。


「討論型世論調査」については、大学一年生のときに政治思想がやりたいと思ってゼミを探していたら、先輩から「うちのゼミで政治思想やれるよ」とほとんど騙されて参加した。討論型世論調査は、通常の世論調査に加えて、討論のための資料を読んだり実際にほかの人と議論をしたりしたうえで再び調査をするというもの。ぼくは特に討論の過程で人々の意見がどういうふうに変容するか、「コミュニケーション」の部分に興味があった。

政治的なコミュニケーションで政治思想というと討議倫理、つまり誰しもが納得できるような理想的なコミュニケーションを思想的基盤に置いたハーバーマスが知られていますよね。
ハーバーマス:第二次世界大戦後に多くの著作を生んだドイツの哲学者。学際的な理論家として多くの分野に影響を与える社会理論を生み、特に「コミュニケーション」を中心に意味理論、社会理論、政治理論を生み、人々が誠実かつ精緻にやり取りをする公共性を重視した。主著『公共性の構造転換―市民社会の一カテゴリーについての探究』
討議倫理:ナチス時代に大量虐殺があったことから展開された批判理論というドイツ哲学の潮流を引くハーバーマスは、初期批判理論を展開したアドルノの「アウシュヴィッツが決して繰り返されないように、そしてそれに類することがいつか起こることがないように、みずからの思想と行為に命じること」という道徳的側面を引き継ぎ、万人に開放されていること(公共性)や平等、連帯、正義といったことを重視した。ハーバーマスの理論を展開する上で重要な概念。
そうっすね。ただ、自分は討議倫理よりも現実のコミュニケーションやそれが行われる空間に興味があった。いわゆる研究についてはなにもできてないからあんまり話したくないんだけど、理論と実証の両方やれるのではと思ってて、グラウンデッド・セオリー・アプローチに興味があったかな。
グラウンデッド・セオリー・アプローチ:統計により数値を扱うなどの量的社会科学の手法に対し、批判的な見地から提示された質的研究方法。インタビューをはじめとした「収集されたデータを説明できる中範囲の理論枠組みを構築するためのデータ収集と、その分析に関する体系的で帰納法的なガイドラインから成り立っている2」。つまり、集めたデータを解釈的に分析しつつ、さらなるデータを収集・分析する手法を指す。

大学一年生後半から批評の文脈を抑えつつ、研究についても調査対象に方法論まで意識している人はなかなかいないと思われるので、相当早くから広い範囲の分野を勉強していますよね…それからなぜ研究の道に進まなくなったのでしょう?
大学院に行くのをやめたのは、ある先生から「お前がやってることは研究じゃない」と言われたことが一番直接的な要因。言葉だけだと攻撃的な印象を与えそうだけど、はっきり言ってもらって本当に感謝してる。当時はムカついたが(笑)いまから考えても向いていないと思う。ちゃんとした研究をやると時間がかかってしまうので、せっかちな自分には難しい。
就職と鬱と地域

研究から離れたあとはどのような道を進んでいったのでしょうか?
IT系のウェブメディアに就職した。理由の一つとしては、批評みたいなことに関わり続けたかったから、もう一つはメディアの仕組みがわかるといいと思ったから。あとはインターネットが好きなので、紙じゃないところかなっていう。でも、仕事はやりたくないし私生活でもいろいろあり、1年半で鬱になってしまって会社はやめた。このときは本当に苦しかった。自分で稼ぐのもうまくいかないし、転職もしたくない。大学に戻ろうかと一瞬考えたけど、それもないなと。大学院に進学した人文系の友人たちは、みんなつらそうだったから。

僕は、今現在、人文社会科学系の大学院に進学して絶賛つらい期間中です・・・変化する社会に即した適応も大学には必要ですが、特に人文系の学問の立ち位置は様々な形で存続そのものが過剰に問われてしまっている側面があり、様々な影響を院生に与えていると思います。
 大学×学問の現状認識──学問と社会をめぐる関係を考える
大学×学問の現状認識──学問と社会をめぐる関係を考える
落ち込んでいた自分を見かねて声をかけてくれたのが、世論調査のゼミに誘ってくれた先輩だった。彼も大学院に行って苦しんでいたんだけど、地域おこし協力隊として津和野町に移住して、町内唯一の高校・津和野高校の統廃合危機をなんとかしようという活動をやってた。各地域の都市部で広報活動も実施して、毎年都市部から10名以上の入学者がやってくる時期もあった。先輩に声をかけられた時はヒマだし話を聞きに行ってみたら、地域おこし協力隊としての移住のお誘いだった。
地域おこし協力隊:人口減少や高齢化が進む日本社会において、都市圏からの流入や各地域への定着などを図るための活動を若者を中心に行うために総務省により2009年度から設けられた制度。
 大学×地域の現状認識──経済構造の転換と人口減少社会を見据える
大学×地域の現状認識──経済構造の転換と人口減少社会を見据える

津和野町は福沢諭吉に次いで、特に学術用語に関する翻訳を行った西周の出生地ですよね。訪れた際には観光地化されているものの、石畳が敷かれていることや、周囲の自然環境や文化的施設が、東京をはじめとした都市とは違う異空間を作り上げていると訪れた際に感じました。

でしょ! 津和野は町並みも面白いし、地域おこし協力隊をたくさん入れていて同世代でいろいろ活動してる人がいるから、最初に行ったときに暮らしていくイメージがある程度湧いた。正直ほかに展望もなかったのですぐに移住することにして、地域おこし協力隊として2年半情報発信や教育関連の仕事をやり、その間に並行して、NPO法人bootopiaを立ち上げ、2017年4月に下宿をオープンした。

下宿を立ち上げた具体的な経緯や活動を教えてもらえますか?
教育型下宿は、津和野高校の統廃合危機で生徒をもう少し集めないとねっていう状況を踏まえてつくったもの。津和野で暮らしたり活動したりしてみたいという生徒を都市部から集めて、シェアハウスのように一緒に共同生活する。津和野が観光地だったから人を泊められる物件があり、津和野高校の取り組みも進んでいたから始めることができた下宿には自分以外のスタッフもいるから、この事業だけで暮らすのは難しい。それでいまは島根県立大学で広報周りの仕事をしたり、編集やデザインの仕事をやったりしながらどうにかやってるって感じ。自慢できるようなものではないよ。ただ時間は自分でかなりコントロールできるから『Rhetorica #04』のような箱入り二分冊の本もつくれた(笑)。
おすすめ書籍:『新復興論』『空をゆく巨人』

自由な言論空間が閉鎖していく一方、これまでとは異なる遠くの地域における出会いと生活環境が新しい視点を切り開いていったんですね! 最後に「批評」を学ぶ初学者におすすめの本を教えてもらえますでしょうか?

両著作を読みましたが、まさに「今ここ」ではないものへとジャンプしてしまう大胆さという意味での人文的なものでありつつ、個人の実際の経験談から語られ読みやすい著作でした。具体的に今の社会において、「こんな文化運動がありうるよ」ということを示していると思うと、確かに示唆的な著作ですよね。
ネタバレになりますが、『空をゆく巨人』の最後のほうで唐突に登場する「怒り」という言葉がいまも心に残っています。この本の大きな主題のひとつである「いわき万本桜プロジェクト」は、なぜやっている活動なのか一見するとよくわからないところがあるのですが、プロジェクトを代表する志賀忠重さんの口から、それは「怒りを鎮めるため」だと語られるのです。福島の事故やその後の経過、それに対する視線。「今ここ」で起きている怒りを乗り越えるために、「今この瞬間を越える」行為として、5年後・10年後に咲く桜を植える。文化や運動について考えるうえで、とても大切なことを語っていると思いました。

おわりに──問いかけられる「受肉」されたもの
哲学・批評という抽象的なものに携わりながらも、常に実践性を追求する瀬下さんの活動。Share Studyは直接的に批評の延長線上で展開しはじめたメディアではないものの、立ち上げた当時に流行ったシェアリングエコノミーをはじめとした状況下に影響を受けたものであることを思い出した。『Rhetorica』が生まれた原点を社会的状況を交えて伺い知ることができたインタビューとして興味深く、勉強になる機会だった。
瀬下さんの基本的な姿勢を表すと「受肉する運動」をつくることである。「受肉」とはキリストに神が宿ったというように、抽象的なものが「実際に」顕現することを意味している。ハーバーマスが想定した討議空間も、瀬下さんは「受肉しているとは思えない」と言うが、時に放たれるズバッとした意見はさすが批評活動を行っているものだと感じた。 しかし、本人は自らを「編集者」として位置づけているという。高校生や大学生と地域において関わりつつも、ネット空間で言論を発し、コミュニケーションを取り、アナログな批評誌をも作る瀬下さんがこれからどんな「運動」を編集し、示していくのだろうか。
今後の活躍にも注目していきたい。
- 『[巻頭座談会]瀬下翔太、板貫城二、太田知也 生き延びてしまった10年―ゼロ年代の後始末』P3, Rherotica #04 ↩︎
- キャシー・チャーマズ(2006)『グラウンデッド・セオリー:客観主義的方法と構成主義的方法』(N.K. デンジン[ら編](2006)『質的研究ハンドブック 2巻 質的研究の設計と戦略』に第7章として収録) ↩︎