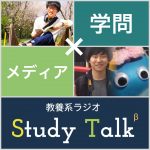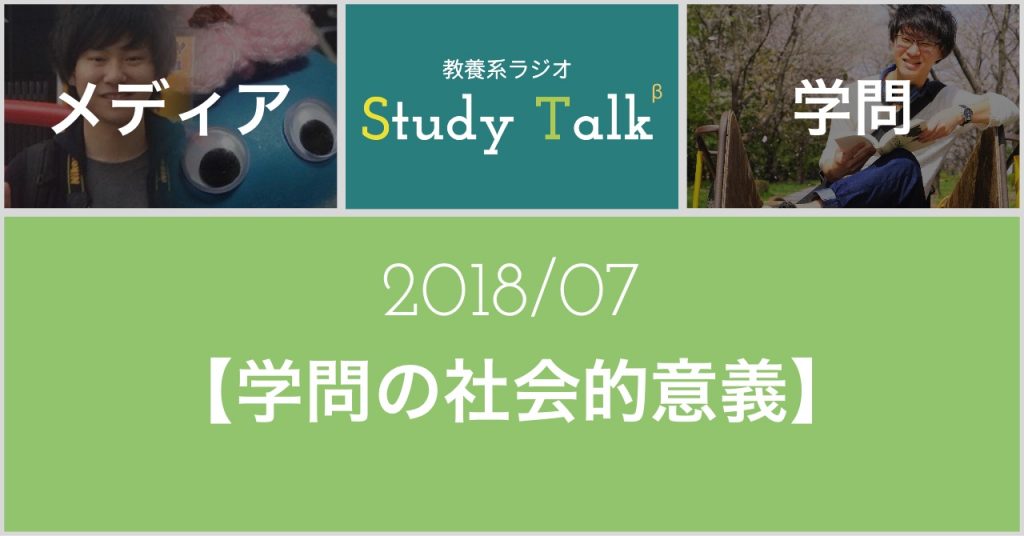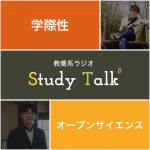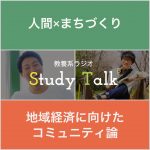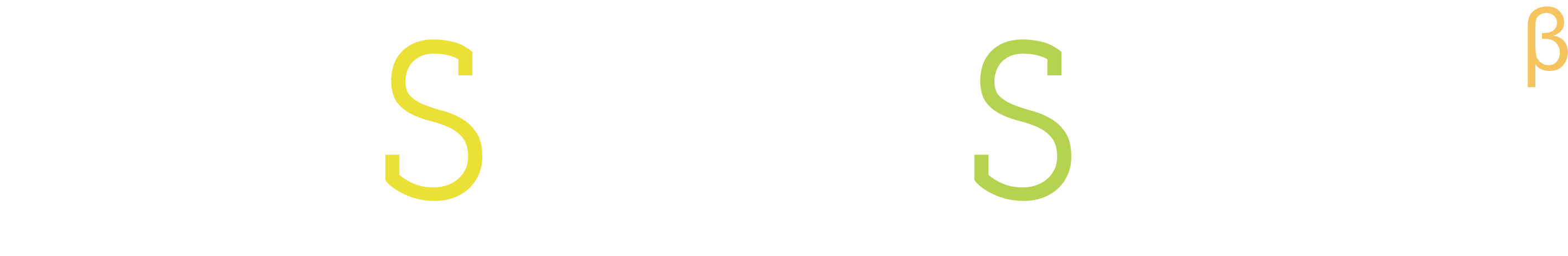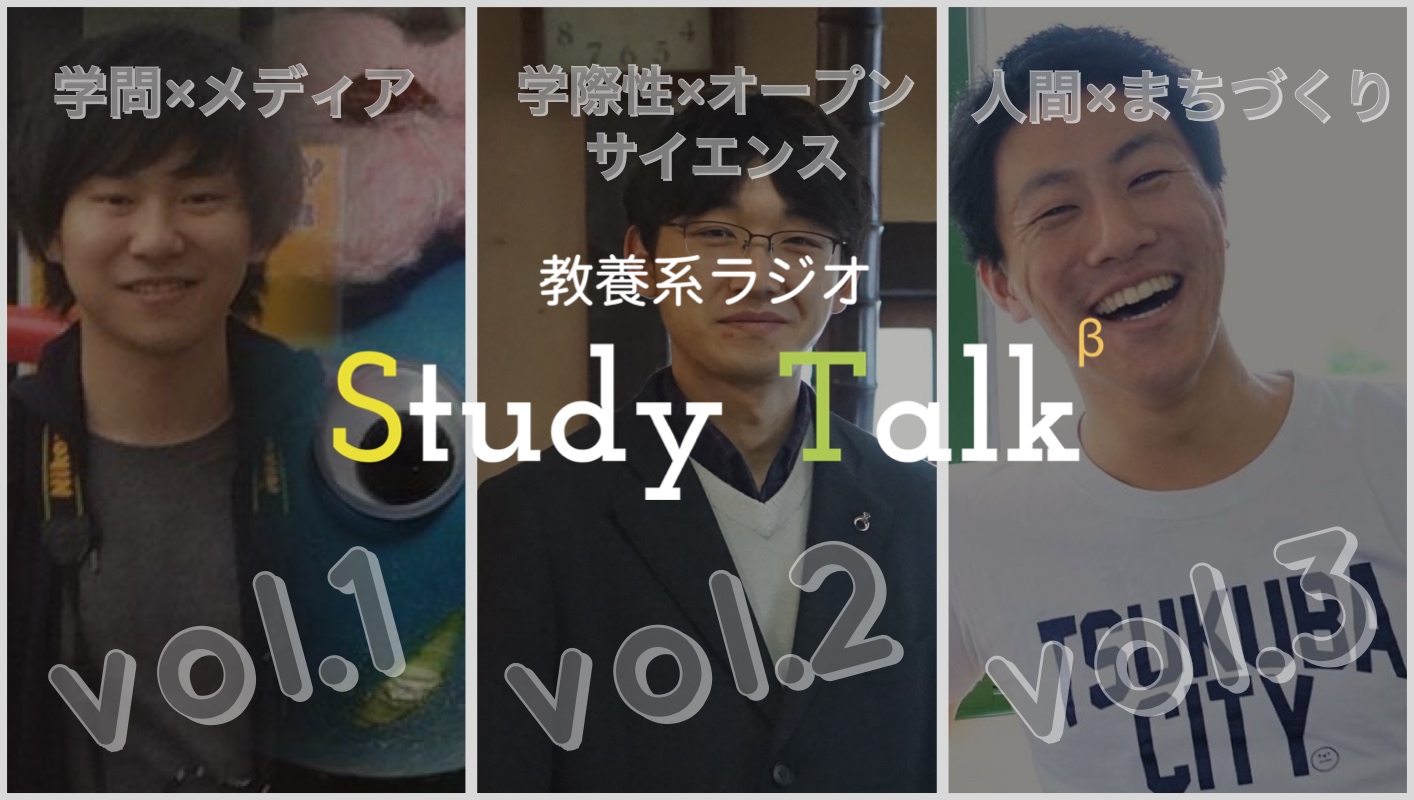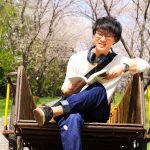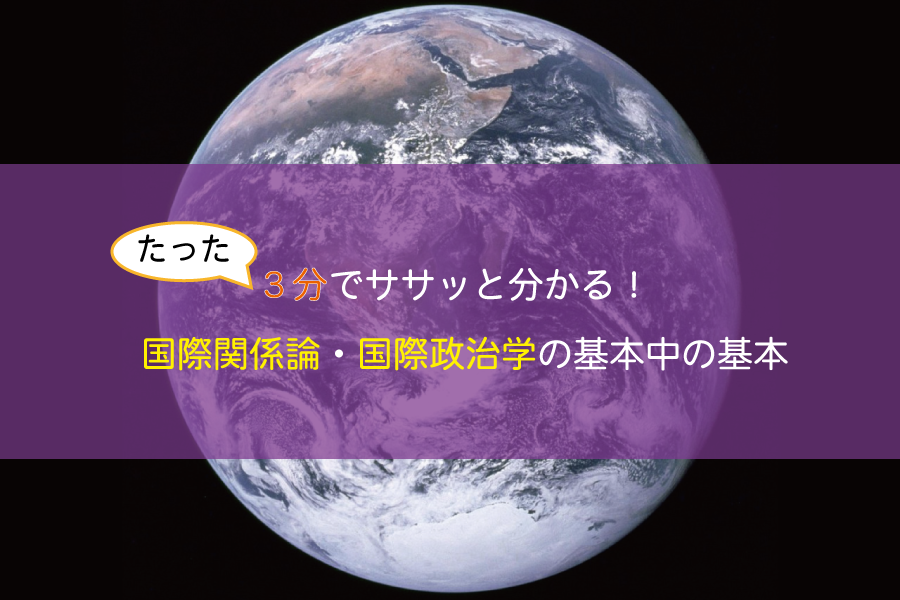Study Talkとは
学問を題材に、沈黙されていることがらを語り起こしていく教養系のラジオ。「Share Study」を立ち上げたとしちるがパーソナリティとなり、毎月ゲストを迎えて二つのキーワードをもとに語り、学び合います。
『教養系ラジオStudy Talk』をはじめ、3つのトークが揃い踏みとなりました。ラジオのパーソナリティを努める、Share Study代表のとしちる(@ture_tiru)です。「学問×メディア」「学際性×オープンサイエンス」「人間×まちづくり」をそれぞれキーワードにし、各ゲストが沈黙を破って語りだす内容とはいったい…!?
それぞれ胸の内をさらけ出したラジオならではの語りとなりましたのでぜひお聞きくださいね!また、それぞれのラジオに呼応して執筆したシェアスタッフのnote記事も展開しております。
まさにShare Studyなフルコースがさまざまに味わえる、Study Talk。お楽しみください!
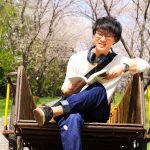
としちる
日本サッカー協会に所属するコーチを目指して筑波大学体育専門学群を目指すも、受験前に父親が逃亡して宅浪生活2年間を送った後、国際総合学類に入学。タイにて日本語指導と留学も経験。専攻は言語人類学、専門はディスコース研究。全国47都道府県をめぐり、「これからの大学(学問×地域×教育)を考えるACADEMIC CAMP!」を主催。運営サイトは4つ、記事執筆数は250以上、「教養」をテーマに活動しています。
vol.1―「学問×メディア」で沈黙を破る!?
1992年生まれ、群馬県出身、茨城県在住。ネット文化研究家。ネットの流行・言葉・文化をわかりやすく解説するウェブサイト『
文脈をつなぐ』を運営。 東京工業大学大学院 理工学研究科 数学専攻卒業(修士)。プラトンやデカルトなど、人文系の古典の本も好き。

木村すらいむ
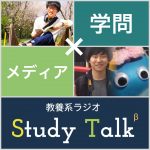
Study Talk vol.1
「学問×メディア」をキーワードに、としちるとゲストの木村すらいむさんで「学問の社会的意義」についてトーク!数学を大学院まで専攻していたすらいむさんは「数学は問を立てて、徹底して基礎から論証していくもの」としてその魅力を語りつつ、としちるは「学問≒問を学ぶ」という観点から「自分自身が問うていくもの」としての側面から語りました。さらに、学問を「メディア」で語っていく者同士、問を共有し、先人や今ここにおける人たちとトークしあうことも、学問の面白さではないかという話に。問うと悩むこともあるけど、先人や知人と共有して問いを深めることができ、自分だけで考えるのではなく、人と一緒に考えることの大事さを学術的な学びを通して知り得るということを語り合いました。
問う、「学問の社会的意義」ってなんだろう?―2018年7月
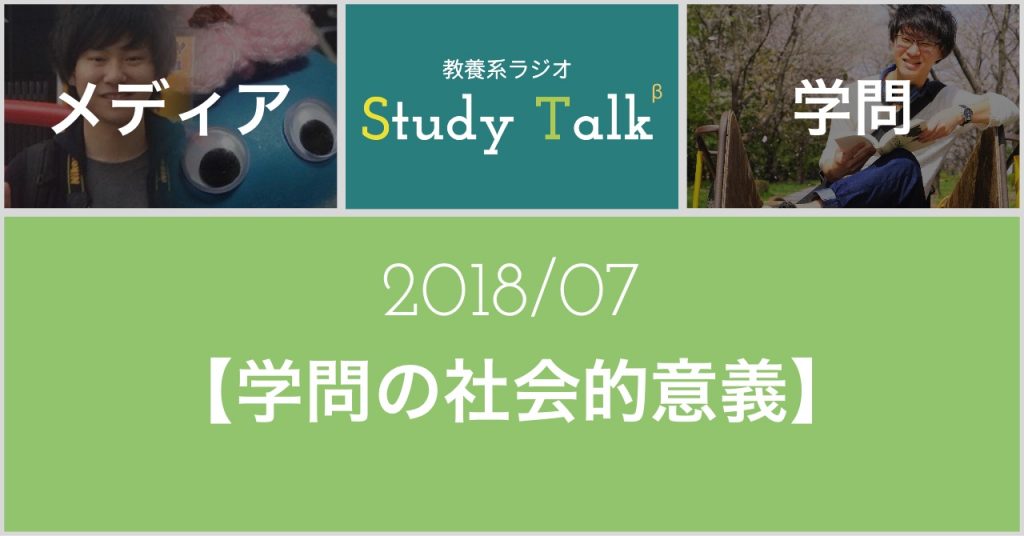
vol.2―「学際性×オープンサイエンス」から考える学問のアマチュアリズム

佐藤究
1996年奈良県生まれ、千葉市美浜区在住の大学院生。東京大学大学院理学系研究科物理学専攻に在籍、大強度陽子加速器研究施設J-PARCにて加速器物理の研究をしている。学部時代は学業の傍らコミュニティ形成に興味を持ち、地域コミュニティによるTEDイベント「TEDx」のスピーカー責任者として運営を行う(中国地方初開催)。KEKサマーチャレンジ、G1カレッジ、ICRRスプリングスクール、ACADEMIC CAMPなどの参加経験を通して現在、学術芸術技術の社会との関わりを思案している。
「学際性×オープンサイエンス」をキーワードに、Share Study代表のとしちるとゲストの佐藤究さんで「学問のアマチュアリズム」についてトーク!物理学を大学院で専攻して研究を行う佐藤さんは「学際性が語られる際の境界線があり、その境界を越える際に”学際性”が語られる」と指摘し、としちるは「そうした境界線があるのは、研究者集団がいることによって、研究を行うためにカテゴライズされた枠組みを構築する必要がその背景にはある」ということを語りました。つまり、「学際性」ということばはあくまでも「研究者」からのまなざしがあってこその「前提」を持つ「物の見方」であり、大学入りたての新入生にとっては「なんでわざわざそんなめんどくさいことをするのだろう」と思ってしまう要因なのではないかと話し合いました。
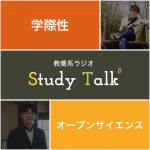
Study Talk vol.2
vol.3―「人間×まちづくり」から考える地域経済に向けたコミュニティ論
1990年9月12日生まれ。熊本県熊本市出身。つくば市在住。Tsukuba Place Lab代表 / グリーンバードつくば リーダー / 株式会社しびっくぱわー 代表取締役 / 合同会社for here 共同代表。筑波大学2年次にコミュニティ拠点として学生カフェ創設にかかわったことからまちづくり分野に興味を持ち、下妻市や水戸市、横浜市などの商店街活性化にかかわった後、2年間京都で武者修行のため移住。関西を中心に行政計画策定に係るコンサルの仕事を始め、のちに起業。つくばに戻り大学生をしながら、2016年12月1日コワーキングプレイスTsukuba Place Labを創業。オープンから1年8か月が経ち、企画運営したイベントは550本以上、来場者は10,000人を突破。「迷ったら全部やる」がモットーで「成功するまで続ければ失敗しない」が信念。絶賛つくば駅前コワーキング “up Tsukuba”準備中!→
つくばを【あげる】コワーキング “up Tsukuba”をつくります!

堀下恭平
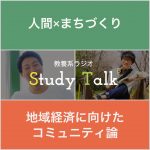
Study Talk vol.3
3.11以降、「地方創生」を旗印としつつ、人口減少を背景に、さまざまな取組がなされてきました。情報技術が発展する中、自由に生きようとする人々が目立ち始める一方、孤独死社会、地域自治体の危機が危ぶまれる昨今の日本における社会情勢です。Study Talk vol.3では、コミュニケーション研究を行うとしちると、行政コンサルタントとしてまちづくり事業に取り組み、経営者としてコワーキングスペースの運営をになう堀下恭平さんと、「人間×まちづくり」をキーワードに「これからの地域経済に向けたコミュニティ」について語り合いました。生命科学系の学部出身の堀下による「動的平衡的なコミュニティ論」と、国際学系の学部出身のとしちるによる「日本文化的なコミュニティ論」が交差するとき、語られるものとはいったい!
まとめのまとめ―語り合い、語りを開く
『知の技法』という1995年に東京大学から出版された大学1・2年生向けのテキストがあります。
この本の「結び」には『「うなずきあい」の18年と訣れて』という副題が付けられています。一部を引用しましょう。
意見は作るものです。ある議論に対して、意見やコメントが自然に湧いてくると思うのは間違いです。あなたがたとえばセミナーの参加者で、その道の達人でなければ、適切な発言をするためには「なにか発言してやろう」と最初から意識的に心がけることが必要です。
セミナーの中で議論を行うことの全般にわたる難しさは、演習の内容や取り組みの熱心さといった水準よりも深いところで、「うなずきあいの18年」間に鍛え上げた同意の技術が、不同意の意見を作り、言うことを妨げていることにあります。
『知の技法』のコンセプトにあるのは「知」は技術であり方法であり、それを(当時の)第一線の研究者から学び得ることでした。つまり、一定の『知の技法』に関する知見を身に着けたあとに目指されるのは、実際に口を動かすことで他者と語り、足を動かすことで資料を集め、実際に分析や論及の技術を身に着けていくプロセスを経験することです。ですから、まず第一に情報を得てできることは語ることです。できることなら語り合うことが良いのです。
自分はどこまで知り得ているのか、何を知り得ていないのか、どういった価値観を前提として持っているのか。
こうしたことを知り得るためには、まずは語ってみること、書いてみることです。
今回のラジオにおけるトークでも、語りの中で各々が各々の学びを「まさにその中で」得ていっていたのでした。それはすぐに分かりえるものではないかもしれません。ふとした疑問などはそう簡単に分かるようなものでもないでしょう。探せば未知はまだまだ広がっています。場合によっては「未知」だのと言ってられない、差し迫った問題もあります。ですが、未知を探る緊張感や、未知が既知となる喜びはまた格別です。
Study Talkは知ること、ぶつけ合うこと、時に自分を壊していく、学びの中にあるそんな喜びや楽しさ(ある意味ではスリリングさ)を表現できないかと思い、はじめました。今後も月1で随時更新していきますので、お楽しみください!
知の技法
小林康夫/船曳建夫(編)、1994年4月8日、東京大学出版会