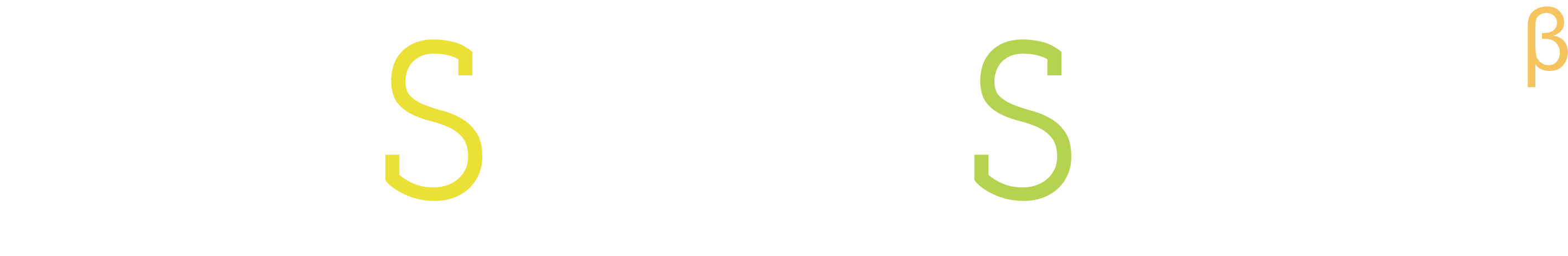Study Talkとは
学問を題材に、沈黙されていることがらを語り起こしていく教養系のラジオ。「Share Study」を立ち上げたとしちるがパーソナリティとなり、毎月ゲストを迎えて二つのキーワードをもとに語り、学び合います。
キーワード
研究×コミュニティ
トークテーマ
つくばではなぜ研究者のつながりが生み出せないか?
概要
Study Talk vol.7のゲストは茨城県つくば市のつくば駅前に立地するコワーキングスペースup Tsukubaでコミュニティマネージャーとして活動する江本珠理さんです。コミュニティマネージャーは、人と人が入り混じる「場」を紡ぐお仕事です。
つくばは「研究学園都市」と呼ばれるように、研究機関が周りに点在し、筑波大学といった総合大学が立地しているのが一つの特徴となる地域です。つくばに住み、異なる分野の人と交流を交わしたい研究に関わる人びとからは「つくばでは研究者のコミュニティがない」という意見がたびたびあがってきました。
江本珠理さんは「場があるから人が集うわけではないですよ」と朗らかに語ります。では、どうすれば人が集う「場」が生まれるのでしょうか?一つの答えとしてあるのが「間を媒介する人や仕掛け」です。言い換えれば、第三者として間を紡ぐ人やそうしたことを成り立たせる機会が必要でしょう。「場」に根差し、時に軽やかに「場」を越境してきた江本珠理さんにこれまでの活動の経験や考えをお聞きします。
番組

スピーカー
◯としちる
日本サッカー協会に所属するコーチを目指して筑波大学体育専門学群を目指すも、宅浪生活2年間を送った後、国際総合学類に入学。タイにて日本語指導と留学も経験。専攻は言語人類学、専門はディスコース研究。全国47都道府県をめぐり、「これからの大学(学問×地域×教育)を考えるACADEMIC CAMP!」を主催。運営サイトは4つ、記事執筆数は250以上、「教養」をテーマに活動しています。
◯江本珠理
合同会社for here代表社員/つくば駅前コワーキング「up Tsukuba」おかみ/ローカルニュースメディア「つくば経済新聞」編集長。まちに入りながら、地域と関係していく「場」づくりを生業にメディアなどでの記事執筆などを行う。
ピックアップ場面
03:30:質問1「仕事・専門にしていることはなんですか?」
「つくば市内」をフィールドにして、コワーキングスペース「up Tsukuba」を運営しながら「場作り」を行いつつ、ローカルニュースサイト『つくば経済新聞』を運営している。お客さんであり、お客さんではないup Tsukubaの会員さんとの関係を紡ぐために、日常のコミュニケーションやイベント運営の際に「隙」をデザインするお仕事をするのがコミュニティマネージャーの仕事の一つ。
07:06 :質問2「自分を一言で表すとどんな人?」
人の感情などに大きく影響されるので「(沼の)水」。あまりこだわりはなく、影響を受けやすい。up Tsukubaの会員さんにもダメ出しされることが多い。
09:00 :質問3「最近、一番驚いたことはなんですか?」
「Wow」と気づいたことが「お客さんのことをあまり考えてなかった」。何か意見を述べるときに特に「主語に『私は』にする」ことを強く意識していた。今はup Tsukubaでよりよい経験をしてもらうことを意識し始め、「I」の経験を高めるだけではなく、「You」の体験をどうやって高められるかを考え始めている。up Tsukubaの会員さんには「You」だけではなく「We」でもあることに気づき、「I」のかたまりから「We」の領域へと認識が広がったことに「Wow」と驚きを得た。
15:20 :質問4「どんな「学びの流儀」を持っていますか?」
他者(オウム真理教 etc.)との境界線は確固としたものなのではなく「ゆらぎ」のあるものであると考えている。具体的なフィールド(中東、つくば etc.)や活動(復興支援)にいるときに出会う他者とも、安易にカテゴライズせず、「本質は一つ」だと思って接している。つまり、アナロジーを駆使している。