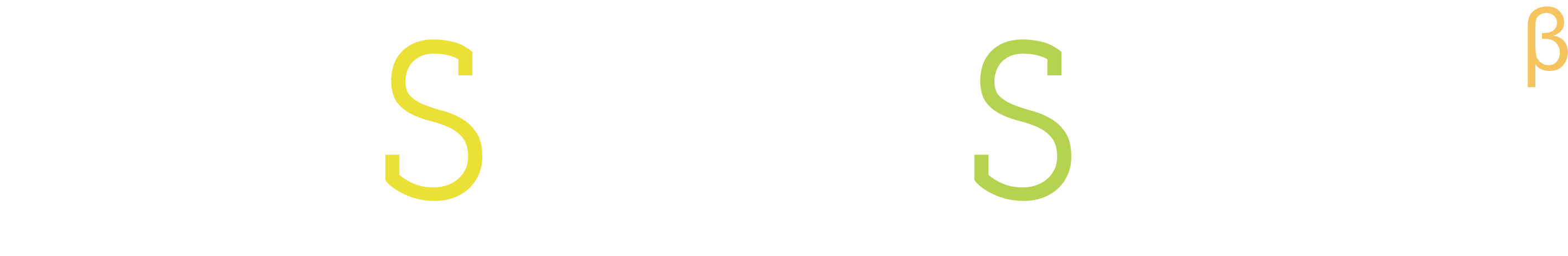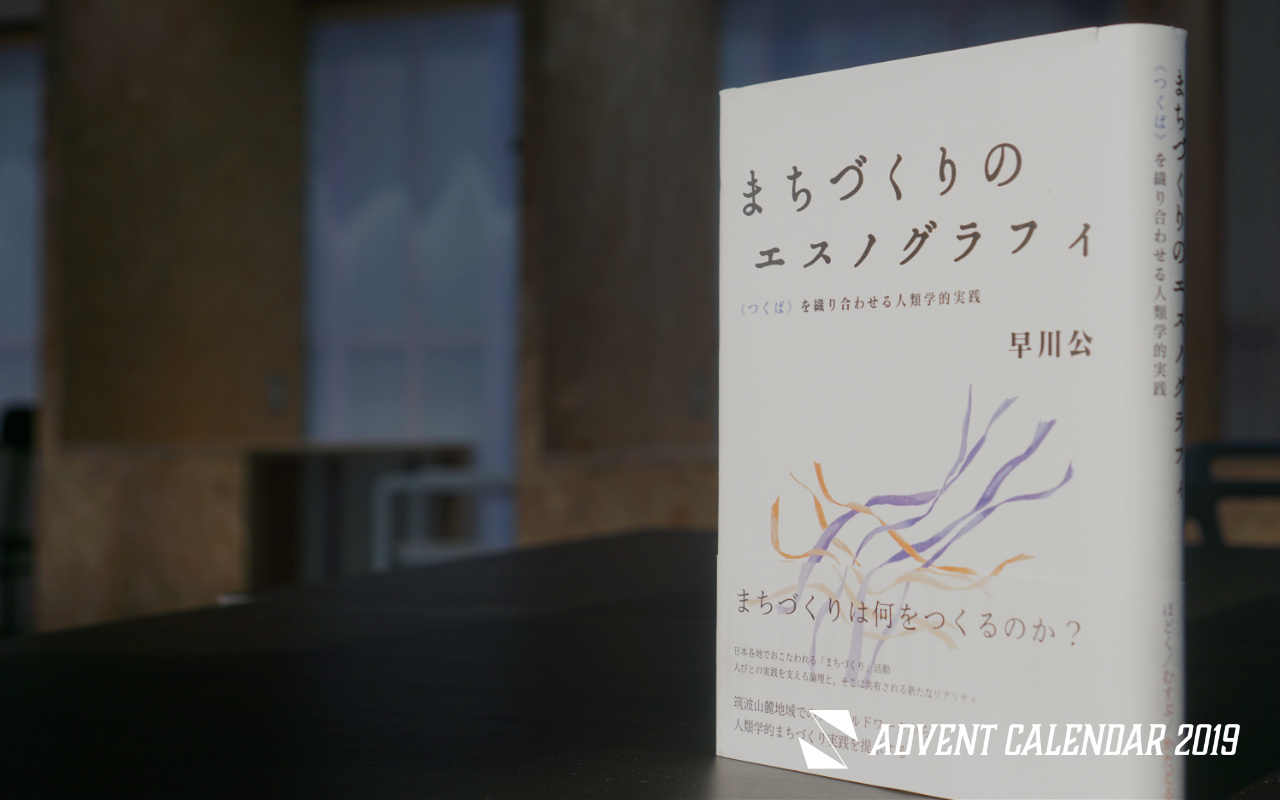こんにちは、早川公と申します。専門は文化人類学で、研究テーマは国内のまちづくり活動(とくにつくば市北条地区)を対象としています。大学教員をやっていまして、現在は大阪のとある大学の経営経済学部で「地域みらいづくりコース」という名の地域志向教育プログラムを企画運営しています。今回の企画テーマは「日常の視点が思わずゆらぐ」です。このテーマを受け取ったときにぼくが直観的に思い起こしたのが、今自分が地域志向教育の中で育成したいと思っている「主体性」についてでした。ぼくは学生の時にまちづくりプロジェクトに関わっている頃からつねづね「問題の当事者でもない自分が関わる意味」について考えていました。その時、一緒に活動をしていた後輩のMがこんなことを言ったのを覚えています。
なんで北条にこんなに関わるのかって聞かれても難しいよね。「呼ばれた」っていうの一番ぴったりくるのかな。地元なわけでもないのに、なんだろうね。
「主体性」は、自分の意志と責任で選び取って行動するニュアンスが強い言葉です。でもぼくらは、そこまで計算し、判断して関わりを決めたわけではなかった。ではぼくらを動かしているものは何なのか。当事者と外部者の間にある埋められないナニカとそこでの葛藤については平岡さんの記事(地域研修プログラムで起こりうる「這い回る経験主義」とは?)にも書かれていますが、本記事ではそれを「中動態」という概念を足掛かりに考えてみたいと思います。
というのも、昨今のまちづくりや教育の世界では、しばしば「自分からやるか」と「他人にやらされるか」という「能動」と「受動」の対立が問題になります。中動態は、そうした意志とは別の基準でできた理解の枠組みを示してくれる概念です。それでは、それが今自分が携わっている学問や教育の話とどうつながるのか、みていくことにしましょう。
ADVENT CALENDAR 2019―21日の投稿

12月1日から24日までクリスマスを待つまでに1日に1つカレンダーを空けるという風習に習って、記事を投稿するイベント、それがADVENT CALENDAR!
文化人類学ってなに?
このサイトの読者には文化人類学に馴染みのない方もいると思うので少しだけ人類学について説明しようと思います。
(いろいろな学問分野や立場の人が「一堂」に会して連載するのもShare Studyの魅力ですよね。)
人類学はその名のとおりヒト(人類)の普遍性と多様性を研究する学問で、大きく遺伝や形質(骨など)を扱う自然人類学と、後天的に習得する文化や社会の観点からヒトについて考える文化人類学に分かれます。文化人類学は、もともと遠く離れた社会(非西欧社会)に赴いて研究する性格が強かったのですが、この半世紀の学問的蓄積をもとに現在は自らの社会のあり様について考え、場合によっては実践に積極的に関与する研究も増えてきました。ぼくの研究者の立場も、こうした流れに位置づいています。
地域思考教育とは?
さて、そんなぼくが今大学で担当しているのは文化人類学の講義ではありません。ぼくはこれまで、(アカデミアという業界の流れに翻弄されたキャリアを送ってきているので)「人類学」と名のつく科目を教えたことがありません。ぼくがこれまでに任された科目の多くは、文化人類学の方法論の一つであるフィールドワークに基づいた地域での実習です。この実習では、地域の様々な問題ー商店街活性化、観光振興、農山村の過疎対策、地域コミュニティの再生などーが取り上げられます。こうした問題は既存の学問分野(ディシピリンともいいます)で取り組むことが難しいため、ディシピリンを横断して取り組むための方法が求められています。この実践をする場が地域であり、そうした実践ができる人、自ら積極的に動ける人間を育てようというのが地域志向教育です。
これは、単一の教員、単一の授業(ゼミ)でどうにかなる問題ではなく、育成する人間像を考えたり、それに伴って学部・学科の学びの設計をすることが必要になります。だからぼくは、自分の担当科目はもちろん、それをはみ出したところで同僚の教職員の方々と一緒にプログラムを企画している、というわけです。
この地域志向教育の運営に、これまで今のところを合わせて3つの大学で関わってきました。その中で、いまぼくが関心をもって取り組んでいるのは、教育における学生の「主体性」をいかに発現させるかというところです。「主体性」ないし「主体的な学び」は、新学習指導要領にも書かれている「大事なこと」とされています。
でも根本的な話で、「主体性を発現させる」ってすごく違和感がありますよね。学生が主体的に学ぶのって、それは当人の問題であって教員にコントロールできるのかというそもそもな疑問が浮かびます。たとえば地域志向教育において、地域課題を提示されて「この課題の解決案を考えほしい」という建て付けで授業があった場合に、学生が「主体性を発現させる」とはどういう状態をもって判断できるのでしょうか。
毎回の授業に出席すること?…違いますよね。
素晴らしい解決案をパワーポイントで綺麗にまとめてすばらしいプレゼンをすること?…うーん、違うでしょう。
そもそも、課題が誰かによって提示されている時点で主体的に学んでいるといえるのでしょうか。その科目を履修を自分で選んだから主体的?でもそれが必修だったら?…そんな風に考えると、学生が自ら「する」とか「される」とかそういう語彙で考えようとすることに無理があるのかもしれません。
「する」とか「される」とか、「行為の主体」を問題にする立場とは異なる視座から主体性について考える…そんなことがはたしてできるのでしょうか。
中動態とは?
そんなモヤモヤを抱えている際に出合ったのが、哲学者 國分功一郎による「中動態」という概念でした。國分は、言語学者パンヴェニストを中心に各時代・地域の哲学者・言語学者らを参照しながら、文法規則にかつて存在した「する・能動・active」 でも「される・受動・passive」でもない「中動」という動詞の態voiceを説明します。
國分は過去を紐解きながら、中動態は、(その語から連想されるように)能動態と受動態の中間にあるものではなく、かつて能動との概念的な対立で構成されるものであったと考察します。それは、一言でいうと次の引用のとおりです。
能動と受動の対立においては、するかされるかがが問題になるのだった。それに対し、能動と中動の対立においては、主語が過程の外にあるか内にあるかが問題になる。(p.88)
ぼくらの認識する世界の行為は、「する/される」の対立で説明されます。なぜそうなっているかというと、ぼくらはそう習ってきたからです。だから教育においても、そのあり方は「自分から進んで学ぶ」か「受け身で学ばされる」かと考えてしまいがちです。でもそれは、ある時代のある地域に規定された考え方の一つにすぎません。中動態は、「する/される」ではなく「主語が過程の外にあるか/内にあるか」で世界を理解する地平をぼくらに拓いてくれるのです。そうした中動態しかとらない動詞の例として、國分はパンヴェニストがまとめた表を示します(p.87)。
生まれる。死ぬ。ついて行く・続いてくる。主となる・わが物とする。寝ている。座っている。故郷に帰る。享受する・利益を得る。被る・耐え忍ぶ。心が動揺する。構う・気にかける。話す。
これらの語をみると、能動/受動で基準とされる「意志」の範疇にない語がみられます。人は基本的に自らの意志で「生まれる」わけでも「死ぬ」わけでもありませんし、意志の力で「寝ている」をコントロールするのは難しいです。ではそれらが完全な受動であるかといえば、必ずしもそうだとはいえません。上の例でいえば、「心が動揺する」のは、ナニカが自分に起きてそれによって自分の中に変化が起こるからなわけですが、ナニカが起こったから必ずそうなるわけではありません。逆に、意志の力でもってそれを完全に防げるわけでもありません。個人的に興味深いと思うのは中動態の語のリストの中に「故郷に帰る」が入っている点です。Uターン・Iターンの人が地域の活動に関わっていることと関連付けてしまいたくなります。
つまり、能動/中動の地平では、行為する人の「意志」がその区別の基準になるのではなく、前者は「動詞が主語から出発して主語の外で完遂する過程」、後者は「主語が過程の内部にあり、動詞は主語がその座になるような過程」であり、両者の区別の基準は「主語の位置づけ」ということになります(p.88)。ぼくらは外部の原因から刺激を受けますが、それだけで変えられてしまうわけではありません。大切なことは、その外部の作用によって、ぼくの中に内向して変化を生じ、それが感情や行動となってあらわれることなのです。
おわりに わたしを織り合わせる意味
「主体的に地域に関わる」という言い方をするとき、ぼくらは無意識に意志をその起点に置きがちです。しかしそれは、(地域で活動したことのある人は直観的に分かると思いますが)すべてが自己決定や判断に基づいたものではなく、成り行きや偶然の出合いや巻き込まれの中で関わりができあがっていきます。冒頭のMの言葉は、まさにそうした状況を言い当てたとものです。
また、地域志向教育のくだりでぼくは「素晴らしいプレゼンをつくって提案する」のが主体性なのかという違和感を表明しました。これを中動態の考えから解釈すると、ぼくがこうした課題解決案を提案するだけの授業に違和感(ないし嫌悪感)を覚えるのは、それが「能動/中動」の世界でいえば、「主語の外で完遂」しているからなのかもしれません。主体性はたしかに重要な概念かもしれませんが、その後で本来大切にするべきものは、既存の「能動/受動」の枠組みではすくいとれないナニカなのかもしれません。中動態はそのナニカを教えてくれるような気がします。つまり、これからの地域志向教育ひいてはその先の地域づくりに必要なのは、中動態の考えに示されるような、外部からの刺激を自分に対するものとして受け取ってしまい、内向的に自分が変わることで外部への「関わりengagement」ができる存在なのではないでしょうか。
(その例の一人が、本企画の第2回記事を担当している江本さんかなと。)
これは、文化人類学における課題の一つである「文化人類学者が社会や公共の領域にいかに関わっていくか」にも連なる問題設定です。当事者でも完全な外部者でもない文化人類学者が関わるための具体的な仕方をわたしの本では「織り合わせ」と表現していますが、外部の世界にもとで自分(わたし)を編み込んでいくという意味で中動態的ともいえるかもしれません。
このあたりの関係は学術的に丁寧に考えていく必要がありますが(只今論文準備中)、当面は「織り合わせ」ていくことの意味と意義を研究と実践のあわいで考え続けたいと思っています。
記事に書いたようなことを、これからも一緒に考えていける仲間を探しています。さしあたり、『まちづくりのエスノグラフィ』の購入者Facebookグループをつくり、そこで議論していくつもりです。もし興味のある方は、Researchmapに掲載の連絡先までお願いします。