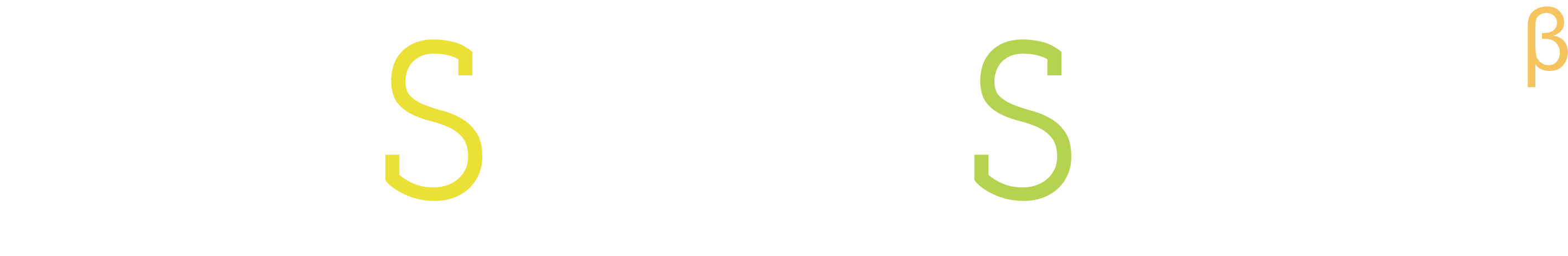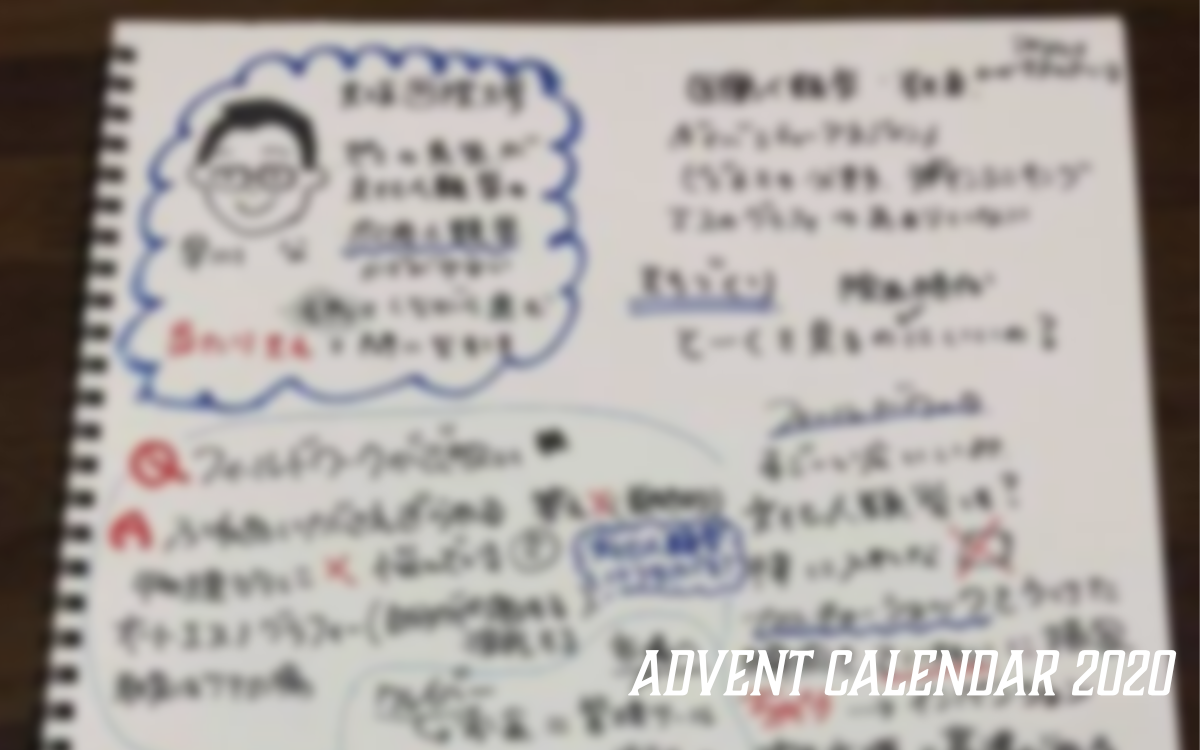こんにちは、大阪で大学教員をしている早川と申します。
Share Studyさんでは、何度か記事を寄稿しています。昨年のADVENT CALENDARではこんな記事をあげたのでした。
今回は、COVID-19の世界的な流行に伴うパンデミックを経て、大学教員・研究者として新しく取り組んだ活動をふりかえりながら、じぶんの「仕事」を再定義してみようと思います。それはきっと、大学関係者以外の読者の方にも、じぶんというものをメタに捉えることに役に立つんじゃないかなと思っています。
ADVENT CALENDAR 2020―23日の投稿

12月1日から24日までクリスマスを待つまでに1日に1つカレンダーを空けるという風習に習って、記事を投稿するイベント、それがADVENT CALENDAR!
COVID-19パンデミックで変わった仕事内容
例外にもれず、大学教員・研究者としてのじぶんの仕事は大きく変わりました。12月19日の記事にも書いている方がいますが、わたしも同じように遠隔授業への対応として、ZoomやYoutube、またGoogle Classroomなどに習熟することに追われました。また、地域志向教育という、学外での体験に基づく演習を担当する立場としても今回は苦労することになりました(そしてこちらはまだ未解決…)。
一方で、研究の方はどうかというと、こちらも大きく変わりました。まずじぶんの研究方法であったフィールドワークができません。研究対象の地域には行けず、加えてそれまで月に一度か二度はあった学会や研究会の出張も見事に消えました。所属先の大学では3月に出張の自粛が通達されたと記憶していますが、夏季休暇のある時にふと「あ、この半年、市外に出てない」と気付くほどでした。
逆に考えるんだ、集まらなくてもいいって考えるんだ
それでは、誰かと議論したり話したりする機会が減ったかというと、そうではありません。これも多くの研究者が体感したとおり、Zoom等のWeb会議ツールにより、研究会に参加する回数はむしろ増えました。実際やってみると、かなりの程度で研究会はオンラインで事足りました。もちろん、研究会にはそれに付随するインフォーマルな場の重要性もあるにはあるのですが、集まらなくてもできるんだ、というのは静かな衝撃でした。
さらに、ぼくにとって大きなインパクトだったのは、研究者と研究会をオンラインでできることよりも、非研究者(とここではひとます対比的に書きますが)と集まらなくてもコミュニケーションができることでした。それまで、いわゆる「社会」に向けて自分が話す時というのは、大学の社会貢献講座とか、自治体での講演や何とか委員会の委員とかそういうことに限られていました。それが、Webで募集をかける中で「そんな話なら聞いてみたい」という声がいくつもあったのは素直な驚きでした。しかも興味があるという話が、文化人類学だというから驚きです。
「社会」に向けて話しかけてみた
文化人類学とは、当たり前を問い直し、わかりなおす学問だ。こうした話は以前にShare Studyにも書きました。
この1年は、世の中の当たり前がガラガラと音を立てて崩れていくことばかりでした。だからなのか、これまで会うことのなかった業界や業種の人、あるいは旧知の友人から「文化人類学の話が聞きたい/話してほしい」という相談をいくつかもらい、そのいくつかを形にしてみました。下の写真はそのうちの一つの勉強会の様子を描いたファシグラです。
手前味噌ですが、やってみると思った以上の手応えがありました。「役に立たない」や「すぐ役立つものであってはならない」とすら言われていた文化人類学の知識や方法が、いま目の前の世界をどう理解していいのか踏みとどまる人たちにとって貢献できる可能性があるというのはとてもうれしいことでした。
そんな体験を幾度か重ねて、気がついたことがあります。ぼくの関心は応用人類学、すなわち文化人類学をいかに社会に役立てるかというところにあったわけですが、その範囲は研究テーマでもある「まちづくり/地域づくり」に限ったところで考えていました。さらに「人類学を教える」という点ことについては大学教育という制度の中で学生に教えることを暗黙の前提にしていました。いわば、じぶん自身が勝手に設定していた「研究」や「教育」の枠組みの中で、仕事することばかりを考えていたのです。
ドットを打ちまくる
ロックダウンの後くらいからぼくは、上に書いたように明確にことばにはなっていませんでしたが、ぼんやりとそのようなことを考えていました。その中でまたまたご縁をもらい、いくつかの媒体でインタビューをしたり知らない分野について原稿を書いてみたりもしてみました。
たとえばこれは、勉強会から一歩踏み出して、実業家の方々と学術とビジネスについて対談してみたイベントです。ちなみに、SEKAI HOTELさんはユニークな「観光」をつくっています。
SEKAI HOTEL note「「互酬性はビジネスに織り込めるのか」 前回大好評だった互酬性シリーズ第二弾の全文がついに公開!」(2020/6/19)
またこれは、障害者とe-sportsとSDGsについて、文化人類学の立場から語るという記事です。「障害」も「e-sports」も専門ではない自分が書くことはとても勇気がいりましたが、Twitterでは好意的なコメントもいただきました。ぼくにとって、SDGsとか包摂とかいう言葉がより実感を伴うようになってきたのもこのあたりからです。
ePARA「文化人類学者・早川公が語る!障害とゲームとSDGs<連載1>(2020/9/4)」
あとは、日本在住の外国人記者から「日本の心」というテーマに基づいて、ぼくの研究関心のまちづくりについて話してみたりもしました。日本を研究対象地域としながら、「日本」あるいは「日本文化」について語るのは正直避けてきたことでした。
Kokoro Media「Anarchic Sustainable Development: A Solution for Japan?」(2020/9/24)
はたまた、「研究者の子育てについて書いてみませんか?」という企画に応募し、文化人類学を胸に留めながら「父二病」という「あえての設定」を生きるエッセイに寄稿してみたりもしました。
日本の研究者出版編『研究者の子育て: 海外・双子・学生結婚・高齢出産・4人兄弟の親たち』 (2020/11/30)
こんな感じで、コネクトするかわからない点(ドット)を、気の赴くまま縁に導かれるままに打ちこむような毎日でした。プランドハップンスタンス?いいえそんな大層なものではありません。本当に、手探りで、糸を撚っていくようなそんな感じだったように思います。
MISC?いいえ、それがわたしの生きる道
こうした、研究に関連するようで関連しない「雑多な仕事」は、研究者の自己紹介ページでおなじみのReseachmapでは、「論文」や「書籍等出版物」というカテゴリーに並んで「MISC」と名付けられています。MISCは「miscellaneous:雑多な、寄せ集めの」の略語のとおり、研究に関連するかしないか、しそうでしない、でもちょっと関連しそうな仕事をまとめて放り込んでいくような枠組みです。たぶん多くの研究者は、MISCを充実させようとは思わないでしょう。
ここで話を飛躍させますが、現在アカデミアをめぐる環境は非常に厳しいものがあります。つい先日も、日本の科学政策に関するNスぺの特集があったように、博士号を取得してもそのまま研究職に就けるのは一部限られている、というよろしくない状況です。
そうした中で、研究者は「本分」であるところの「論文」を充実させようとします。それがポストを得るための大前提になるからです。もちろんそれは大切です。ですが、ぼくはここで、あえて「専門」とは関係ありそうでなさそうなMISCに目を向けてみることも大切なんじゃないか、と言ってみたいのです。
MISCは寄せ集めの入れ物です。なんの役に立つかはわからないけれど、ある場面では小商いのためのスキルになるかもしれないし、またある時は共同研究ののりしろになるかもしれません。「専門」だけで食っていくことが難しいからこそ、MISCという仕事の存在感が出てくるのかもしれません。
じぶんの仕事を考えてみよう
そんなことを書くと、「いまあなたは恵まれた立場にいるからMISCなどといえるのだ」と思う人もいるかもしれません。ですが、ぼく自身決して順風満帆なアカデミックキャリアを登ってきたわけではありません。むしろ、初めてのポスト(1年更新の助教)を得たときの決めては、採用後のBOSSに言わせれば「色々やってるからものになりそう」というものでした。これも生存バイアスと言えばそうなりますが、MISCは身を助くの実例はぼく自身ということになります。
今年は、折しも社会と学術の関係性が関心事にのぼった年でもありました。そのこと自体に言及する力はいまのぼくにはありませんが、じぶん自身としては違った関係のあり方を、そして可能性を、いまはMISCという雑多な寄せ集めの中から、じぶんの仕事と呼べるようなものを紬出していきたいと思っています。
じぶんの「仕事」は「専門」に悩む人たちに、この文章の何かが参考になれば幸いです。