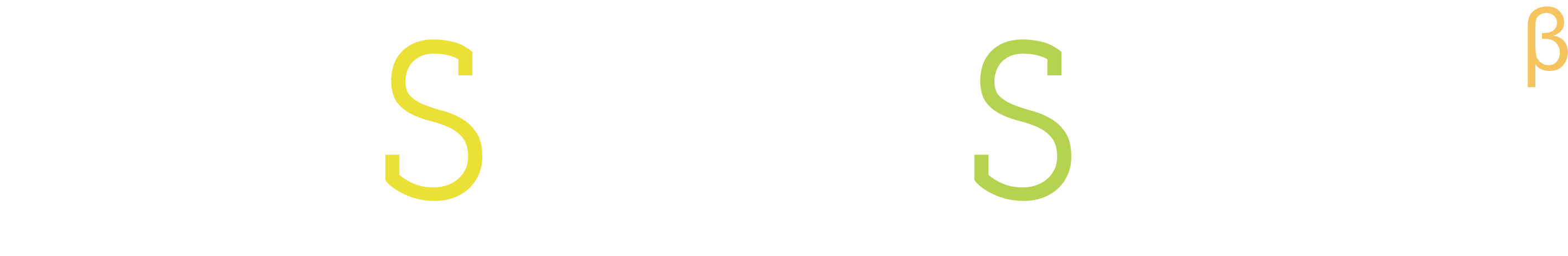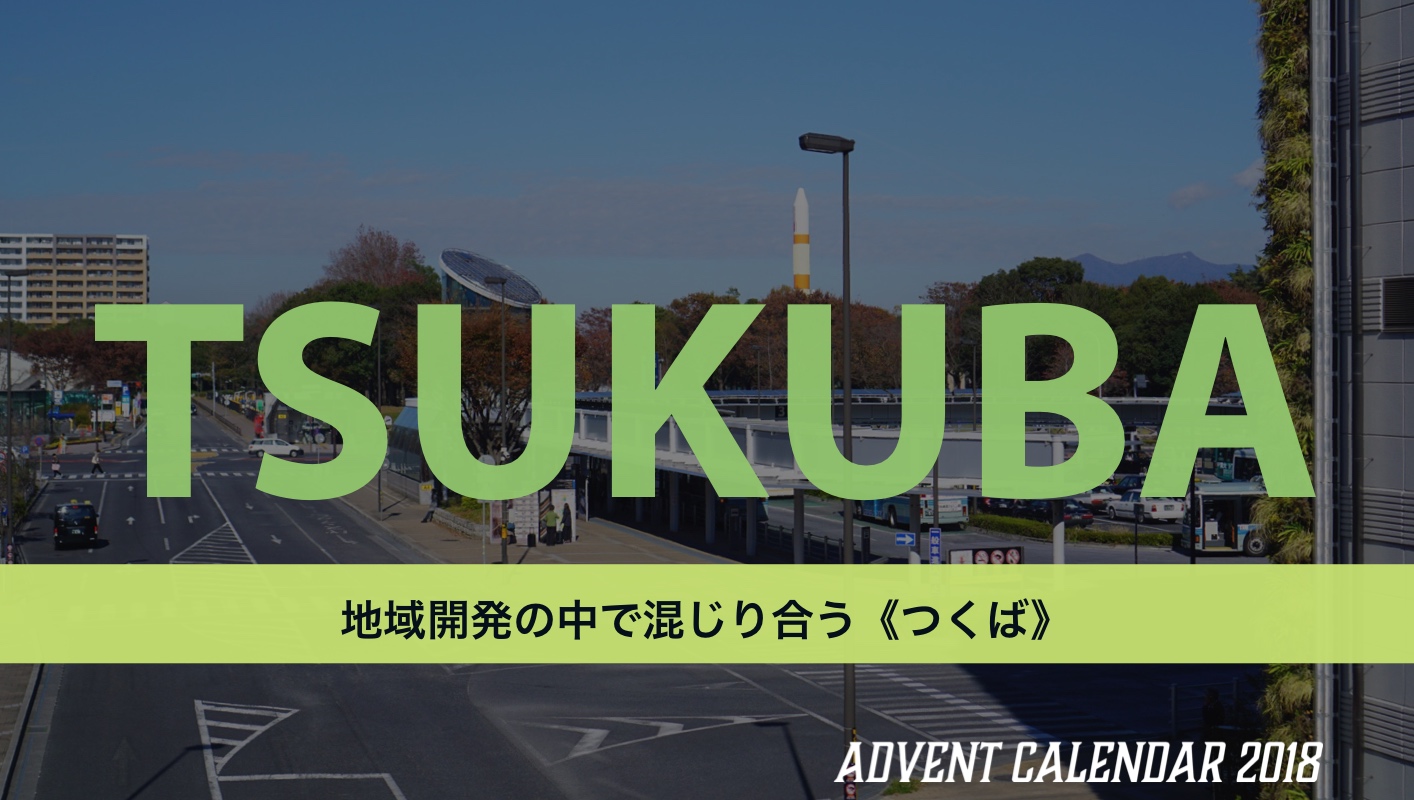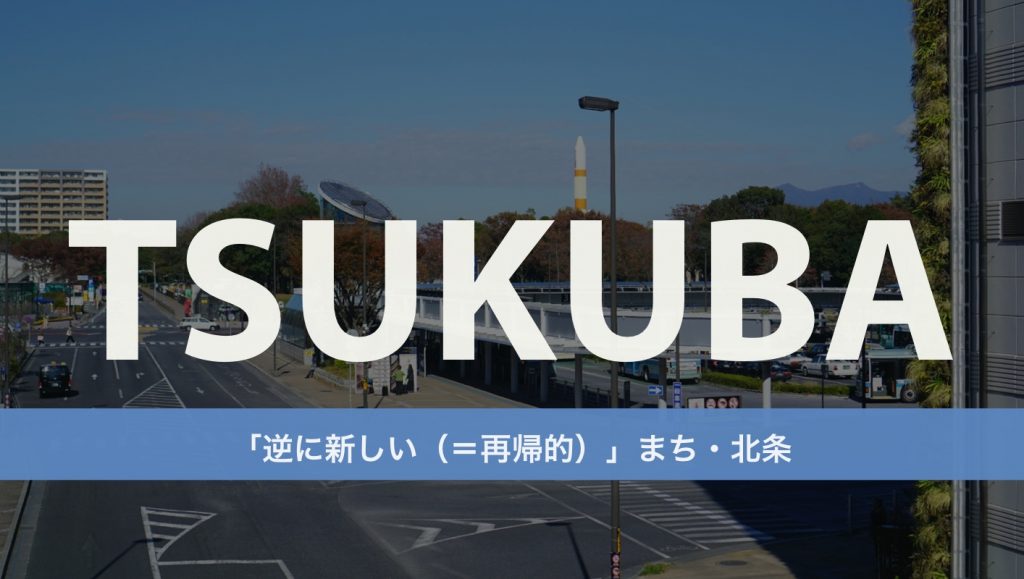こんにちは、早川公です。この記事は、つくば市の地域開発を題材に日本のまちづくりについて考える連載で、今回は第2回目となります。
今回は、地域開発を通じて変わる地域イメージと、それを捉えるための方法について書きます。「地方創生」が叫ばれて数年経ちますが、そのような状況を理解するための「まちづくり文化論 初級編」になれば幸いです。
ADVENT CALENDAR 2018―4日の投稿

12月1日から24日までクリスマスを待つまでに1日に1つカレンダーを空けるという風習に習って、記事を投稿するイベント、それがADVENT CALENDAR!
前回の概要
前回は、筑波研究学園都市開発という「国家的開発プロジェクト」を通じて、今のつくば市がある地域では、「つくば」と「筑波」という2つの空間的イメージができたことを説明しました。それは、「つくば」は「ガクエン」とも呼ばれ、近代的で進歩的に語られる一方、「筑波」は「サンロク」と呼ばれて伝統的で後進的なイメージを移住者から付与されてきた、というものです。
都市建設期に否定的に語られ、周辺化せざるをえなかった「筑波」は、つくば市の誕生後にさまざまな「活性化案」が出されました。当時(1990年代)のつくば市の報告書には、そのなかには、ゴルフ、キャンプ、スカイスポーツや、ブルーベリーのような市場付加価値が高い作物の栽培、また「筑波山麓田園博物館」なる構想もみられます。これらの一部は、今も「筑波」にありますし、ブルーベリーは特産品の1つになっているものの、報告書からは「バブル期のリゾート開発」の香りがにおってきてしまいます。実際、筑波山麓地域にはこの時代に建てられて打ち捨てられた別荘の廃墟がゴロゴロしています。
都市発展期
そんな「筑波」に改めてまなざしが向けられる契機が、つくばエクスプレス(TX)の開通に伴う沿線開発です。それまでの開発は、筑波研究学園という都市を新たに造り出そうというものでしたが、TXの開通は少し開発の方向性が異なります。それはTXが東京へ最速45分で到着する利便性を押し出した「通勤圏としてのつくば」というものです。そこでは、「東京とは違う場所」としての「つくば」が考えられるようになります。その象徴的なコンセプトが「つくばスタイル」です。
つくばスタイル
「つくばスタイル」は、TX沿線開発の事業者である茨城県、つくば市、UR都市機構を中心として、筑波大学や市内のまちづくりコンサルタント、さらには大手広告代理店や出版社を巻き込んで造られたまちのキャッチコピーです。それは、「つくばスタイル協議会」というところで、次のように表現されています。
自然が豊かな街、あるいは都市機能が充実している街は探せば日本中にいくつもあります。しかし、つくばエリアのように<都市><自然><知>がバランスよく融合し調和した場所はそうそうあるものではありません。つくばスタイル。それは、そんな魅力あふれる「つくばエリア」だからこそ手にすることが出来る素敵なライフスタイルのこと。
つくばは都市と自然と知がバランスよく融合して調和した場所。「つくば」と「筑波」として別々のイメージで語られていたものを1つにまとめて融合させたもの、それが「つくばスタイル」という概念になります。
そしてこの「つくばスタイル」は同名の雑誌『つくばスタイル』を通じて、イメージが流通していきます。というか、つくば市民の人はどちらかといえばこの雑誌の方を連想するのではないでしょうか。そのくらい、つくば市では馴染みのある雑誌ですよね。この『つくばスタイル』が、「つくば」と「筑波」の一体的なイメージづくりに貢献します。例えば、第9号の表紙は以下の写真の通りです。
「筑波で見つける古き良きニッポン」と題して、古い店蔵の前で浴衣で佇む若い男女が表紙になっています((ちなみにこの店蔵が、当時ぼくが活動に関わっていた「北条ふれあい館」であり、写真の男女が同時期に別チームだけど一緒に活動をしていた筑波大生の2人です。この辺りは次の次くらいの記事になるでしょうか。))。かつては後進的で古くさいものとされてきた場所が、「逆に新しい」ものとして提示されているのが読み取れます。「東京」ではあえてそうしないとできない暮らしが、「筑波」だと気軽にできるんだ…知的でエコなライフスタイルを送る場所としての「筑波」が『筑波スタイル』として構築されてゆくのです。
弾けて混ざる《つくば》のイメージ
こうして、2005年のTX開通を契機に、地域を表現するイメージは大きく変わっていきます。そこでもっとも大きな影響を与えたのが「つくばスタイル」でした。同時期には他にも「とかいなか」のようなフレーズも考案されていましたが、それほど定着はしていません((「都会」と「田舎」の両方の性質を併せ持つ、という意味で造られた用語です。))。
かつて「陸の孤島」と呼ばれていた街。「筑波」の中に急に「つくば」ができてお互いに積極的な交流がなかったものが、鉄道の開通で一気に「先進的なライフスタイル」の街へとイメージが書き換えられていった。「つくば」の中で混ざる「筑波」と、それによって変わっていく「つくば」それ自体のイメージを、ぼくはここで《つくば》と表現したいと思います。
現在の休日のTXつくば駅では、早朝からカラフルな格好の登山客を頻繁に目にします。そんな風景が当たり前になったのはこの10年の話であり、それは健康志向や里山生活のようなオルタナティヴなライフスタイルが再評価された時期と対応します。《つくば》は、まさにそんなこの10年の現代社会の変化を観察するには絶好の場所だったと言えるのです。
地域認識を捉える方法
ここまで、《つくば》を題材に地域開発を通じて変容する地域のイメージについて扱ってきました。最後に地域の変化を捉える調査の方法について紹介しましょう。
今回の方法は、社会調査では「内容分析」と括られるものです。「各種メディア」を片っ端から集めて、そこに書かれている言葉や画像のイメージを分析します((内容分析は、社会調査士養成の課程では質的調査に分類されますが、昔から特定の話題に関する新聞記事の面積を測る量的性質の研究もあります。また近年では、ソフトウェアの発達も手伝ってテキストマイニングのような文字列の頻出度合いや文字列どうしの相関を図る手法もさかんです。日本における質的な内容分析の古典としては、見田宗介の「現代における不幸の諸類型」、見田宗介(1965)『現代日本の精神構造』弘文堂に所収)のような身の上話の分析が有名です。))。各種メディアは、ぼくの場合、刊行された雑誌、ウェブサイト、市の報告書、市史、個人の体験記、市報(10年分)がそれに相当します。変化はある程度の期間でみていく必要がありますから、そうした場合は各種メディアを対象として分析するのが有効です。
それに加えて、フィールドワークでの色々な方の「思い出話」も補足的に使いました((フィールドワークは、さまざまな学問分野における「現場調査」の総称です。フィールドワークの大まかな分類や方法については、(佐藤郁哉(2006)『フィールドワーク―書を持って街へ出よう』新曜社)がおすすめです。))。色々な方というのは、筑波大学当時1期生の人、「移住第一世代」と自称する夫婦、「筑波」でずっと商売を営んでいる人、などです。思い出話は生々しく楽しいのですが、それが事実と対応しているかについてはよく検討しなければいけません。
ぼくは、そうした聞いた思い出話を市報や市史と突き合わせて確認しつつ、調査をまとめました((1つの情報を複数の媒体や方法で確認することを、社会調査では「トライアンギュレーション(三角測量)」と言います。元々は測量の用語ですね。))。例えば、「つくばと筑波」という言い方は人びとの語りではしばしば出てくるのですが、それが公的な報告書ではいつ表れるのか、と調べることによって、それが「ふんいき」だけでなく「事実」として確認できるようになります。ちなみに、ぼくの調べたところでは、1992年(平成4年)発行の『つくば市北部地域開発構想策定調査』という報告書が「つくばと筑波」の初出でした。
地域開発としてのまちづくりを考えるとき、こうしたその場所が地域内外の人にとってどのようなイメージを持たれているのか、を調べるのはその場所をどういう場所にしていきたいか、というまちづくりの本質的な問題とリンクすることだと思います。今回はそれを《つくば》を舞台に考えてみました。次回の記事では、《つくば》の文脈から離れて「まちづくり」という現象全体にもう少しフォーカスを当ててみようと思います。