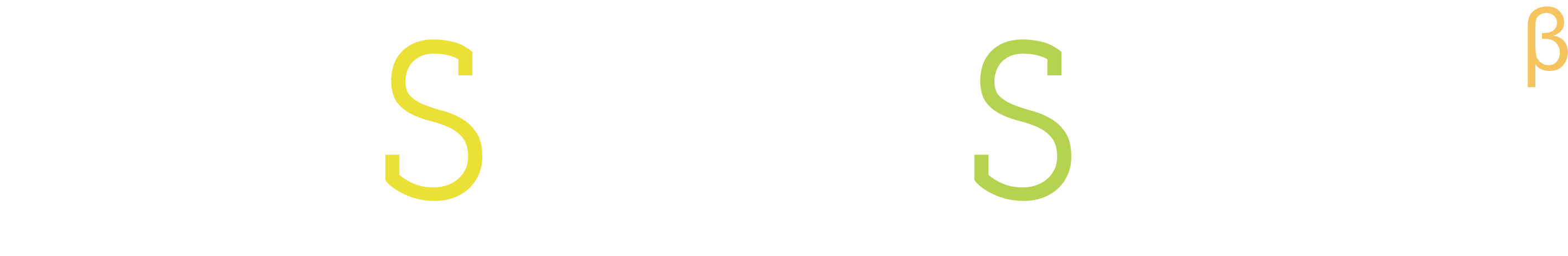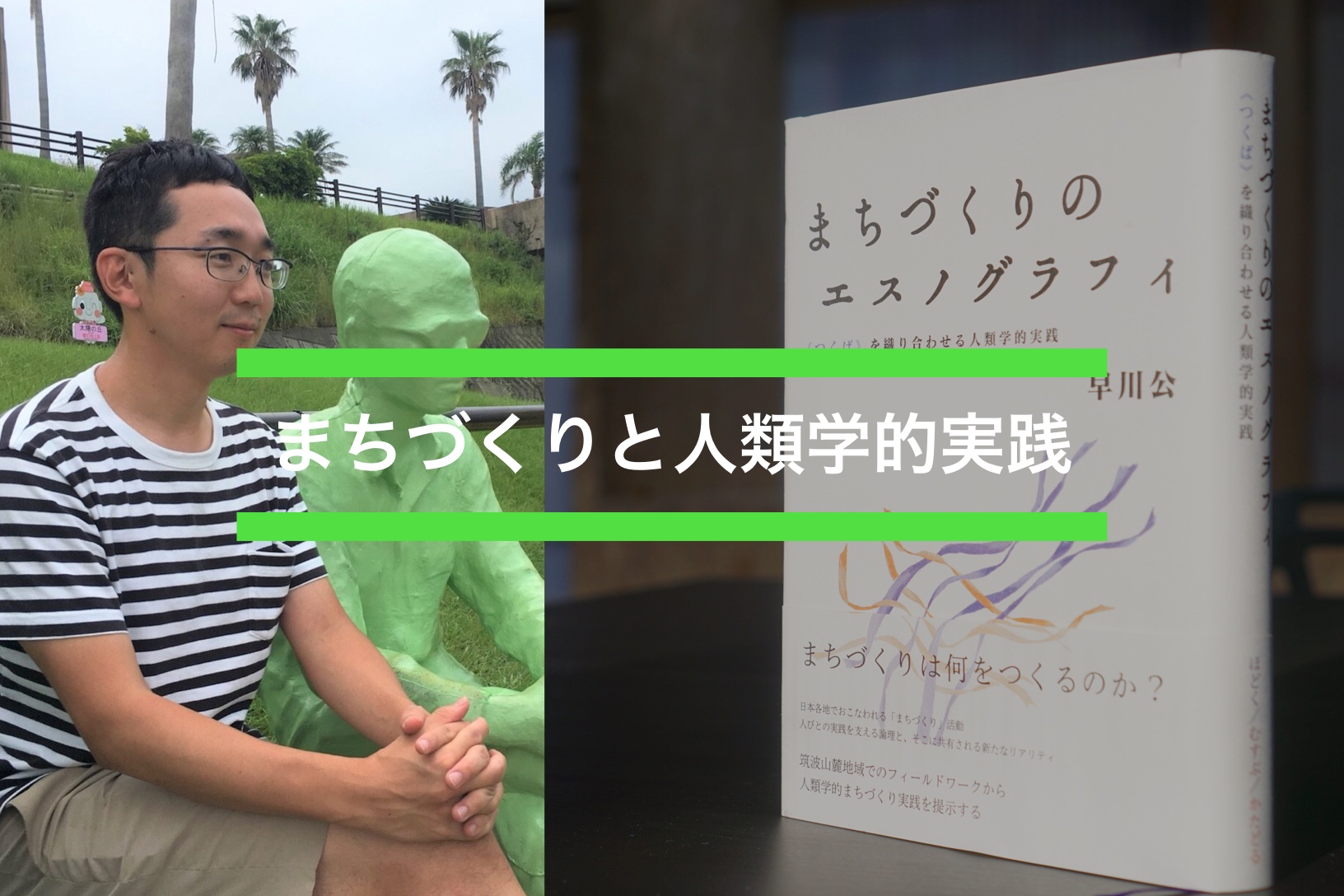こんにちは、早川公です。ありがたいことにもらった連載記事も今回が最後となりました。
この連載の第1回から第3回は、日本の地域開発の展開から誕生した稀有なまちである《つくば》の話から始まり、そこから筑波山麓の北条地区のまちづくりで「発見」された「逆に新しい」という価値観を現代社会の再帰性として考察しました。そして、第4回となる前回の記事では、そのような錯綜したまちづくりの状況を研究するための視点を示し、まちづくりを文化現象として捉える人類学的視点を紹介しました。
一連の記事でぼくが主張したかったこと。それは、「まちづくりに携わる人」、「地域住民の方含め一般の方々や一人ひとりの学生」、さらに言えば「どんな分野の研究者」であれ人類学的実践をしていけるんだ、ということです。
人類学は人びとの行為や生活の社会文化的な意味を記述、分析していく学問です。つまり、一見当たり前の存在として捉えている「人間を分かり直すための学問」が人類学なのです。そうであれば、自分たちが日常的なおこないを振り返ること、さらにはそれが「個人的」なものにとどまるのではなく、「人類」という種の普遍性として読み取れる視点を提供してくれる学問なのです。
人間理解の学問
文化人類学は、教科書的には大航海時代に起源をもつ異文化研究の学問です。つまり、冒険家や宣教師や商人が異国の地へ赴き、そこでの体験を記録したものに基づいて、異文化を考察してきました。この時代の人類学は、次に説明するように自分で調査をするわけではなかったため、安楽椅子の人類学者などと(否定的意味を込めて)呼ばれていました。
西欧近代の相対化
人類学は異文化を研究する学問ですが、18世紀以降、学問的関心の由来は西欧近代の相対化にありました((そこで近代社会の原理を当の社会から分析しようとしたのが社会学の始まりと言われます。社会学と人類学は隣接学問で、現時点でこの違いを明確に説明することは困難に(あるいは意味がそれほど無く)なっていますが、一つの分け方として、社会学は自文化研究、人類学は異文化研究、というのがあります。ただしこの分け方だと、ぱっと見では、他国の社会を研究する国際社会学や、何よりぼくのように日本をフィールドにする人類学はどうなのか、という疑問は当然出てきますよね。ですが、この記事ではここの話には立ち入らずに話を進めることをご容赦ください。))。つまり、近代化によって社会が著しく変化する中で、西欧では色々な社会問題が生じていたわけですが、そうした近代化以前の社会では人間はどのように社会生活を送っていたのか、というのが人類学者の関心であったわけです。そのような関心の向けられる異国は近代社会と対比して未開社会と呼ばれました。この言葉から察せられるように、そこには(あたかも実験室における単純にモデル化された)近代社会の原型をみる考えや、それとは別に、近代社会にはない理想の社会を求める考えもありました。つまり、異文化を通じて自文化を確認するということです。
この「異文化から自文化を振り返ること」ということをさまざまな民族や集団を対象に研究すること、またそれらを学び、自らもフィールドワーカーとして経験を積むことで「人間を分かり直す」というわけです。
フィールドワークという実践
初期の人類学には、調査が書物に限られていたり現地調査もわずかの期間でしかなかったため、未開社会への偏見がどうしても含まれていました。そんな人類学が学問として明確な立場をもつのは、B. マリノフスキーという人類学者の存在です。彼は現地の人びとと共に生活し、現地語でコミュニケートして、彼らの行動様式や世界観を理解する方法を編出します。それが、参与観察(対象と関わりながら観察する)という手法です。この参与観察を中心とするフィールドワークの方法が、人類学が他の学問と一線を画す学問上の特徴となります((ただし社会学においても、シカゴ学派のようにフィールドワークに基づいた素晴らしい社会の分析があります。))。
加えて、マリノフスキーの功績は、異文化を彼らの目線から捉えようとした点にあります。それまで意味のわからない。無駄な、非合理的と見なされていた現地の人びとの行動を、彼らの文脈に位置付けて理解し直すことで、文化的合理性ともいえるものを捉えようとしたのです。
この考えと方法は、西欧近代の相対化の強力なツールとなります。現地の人びとという他者と関わり、そのものの見方を知ることによって、自らのものの見方も文化的に構築されたものである、ということに気づいたわけですから。言い換えれば、他者への関わりを通じて自己を「分かりなおす」学問というところに、人類学の大きな特徴があったのです。客観的にみる、というだけでなく、関わる、という実践が、学問の根底に流れています。
研究と実践の間
ここまで人類学の歴史に簡単に触れながら学問的特徴を見てきましたが、さて、ここらで記事の主題でもある実践について考えて見たいと思います。
人文社会科学では、「研究」と「実践」はしばしば別個のものとして対置されます。「研究者」と「実践者」といった方がよりわかりやすいかもしれません。ぼくも大学院生の時はよくこういう風に言われました。
「あなたは研究をしてるの?それとも実践をしたいの?」
現場に研究者として居るのか、それとも現場の何かしらの問題を解決する実践者としてなのか。これはその渦中にいたぼくにとってはつねづね思い悩むことでした。
しかし、よくよく考えれば、現実の中には「ここまでが研究」で「ここからが実践」などというものは存在しません。実際、わたしが筑波山麓地域でおこなったフィールドワークは、実践者として関わりながら自分自身の活動も含めて関係者のふるまいを描写するものでした。その際に、今は研究者として関わっていて〜、や今は実践活動中なので〜というものが全ての場面で明確になっていたわけではありません。それは現場の中では、その場その場の継ぎ接ぎ(パッチワーク)でしかありません。
改めて、実践とは
実践とは社会科学的にも歴史がある概念ですが、ある区分としては、「意識的な行為」と「慣習的な行為」というものがあります((前者をプラークシス、後者をプラティークと呼ぶことがあります。))。ギリシア哲学においては、前者は政治的な行為を指していて、そうしたアクションが重要であるとされましたし、そののちカントも、これに連なる実践理性の重要性を説いています。
ですが、上に書いたように、現場ではそれらは明確に区分されているわけではなく「ごっちゃ」です。人類学者に限らず、人間の実践とはそういうものです。ぼくたちは、その時々で、色々な立場を自覚したりしなかったりして生きています。自分の政治性を強く意識して発言することもあれば、ふと流れるニュースに「なんとなくムカついて」嫌悪感を覚えるだけのこともあります。例えばつくばのことなんて気に留めないで生活していても、SNSのタイムラインでつくば市が「住みよいまち第何位」と聞いて誇らしく思う自分に気付くこともあるでしょう。ただ人間はそうして、意図的と慣習的を行き来しながら現実を編んでいるわけです。
まちづくりも同じです。一貫してまちづくりのみに人生の全てを捧げる活動家になれる人はごくごくわずかです。それに熱心に関わる人であっても、商売を兼ねていたり、学生だったり、家庭運営があったりするわけです。フィールドでは、誰しもがまず生活者として存在し、その中で無意識に(ルーティンに)生きていながら、ふとした瞬間に「何か」を自覚・知覚し、解釈して行動しているわけです。その「何か」が、地域にある建物だったり特産品だったり、そこに流れる雰囲気だったりするわけで、そして人びとがその「何か」に気づく瞬間を捉えようとする方法がエスノグラフィでした。
織り合わせる
冒頭でぼくは、文化人類学は、他者への関わりを通じて自己を「分かりなおす」学問である、と書きました。そうして考えると、ぼくらは毎日フィールドワークをしているようなものです。実際、R. ワグナーという人類学者はそれを次のような言葉で端的に説明しています。
何処の者であれすべての人間を一種の「フィールドワーカー」と考えればよいかもしれない。(中略)あらゆる人間が「人類学者」だと、それゆえ、文化の発明者だと考えるならば、すべての人々は、コミュニケートし、かつ自らの経験を理解するために、何らかの意味で私たち西洋の集合的「文化」に似た、共有された慣習装置を必要としていることになる((ワグナー, R. (2000)『文化のインベンション』山崎美恵・谷口佳子訳、玉川大学出版部、pp.70-71。))。
現場の人びとは「フィールドワーカー」であり文化の発明者である。その現場の人びとのように、世界を捉え、世界を分かりなおし、それを何かのかたちに設えていく…フィールドワークという方法を採用する人類学における実践の暫定的な回答がこれです。すなわち、神の視点から現象を理解するのでも、没入して問題解決にあたるのでもなく、現場の中で両者を行き来しながら関わること、そしてそれを通じて構想を現実に織り合わせていくこと。
特定の問題解決の手法を洗練させていく専門家・専門分野の存在はこれからも重要です。一方で、そこで際限なく専門分化するのだけでは問題は解決しません。そこで、現場に身を置き、「プロの素人」として右往左往しながら現象の全体性を回復させていく人類学的実践の意義は大切になっていくと思います。「大きな物語」なき現代だからこそ、この社会と自己を織り合わせていく実践に目を向けていく必要があるのではないでしょうか。
終わりに
ここまで、ぼくの連載に付き合ってくださりありがとうございました。一連の記事は、拙著『まちづくりのエスノグラフィ 《つくば》を織り合わせる人類学的実践』をもとに、そのエッセンスを抽出したものです。まちづくりは日本各地で展開されているわけですが、そのまちづくりに関わるなかで、自分の立ち位置や関わり方に疑問が浮かんでいる人や、そもそもまちづくりって何なの?と思う人に読んでもらいたいと思っています。
この連載が、つくばへの興味、人類学への興味、そして自分がすむまちへの関心に向かってくれれば幸いです。
ありがとうございました。
- ぼくとつくば―地域開発(まちづくり)が展開される中での「筑波」と「つくば」
- ぼくとつくば②ー地域開発の中で混じり合う《つくば》
- ぼくとつくば③―「逆に新しい(=再帰的)」まち・北条
- まちづくりと人類学―文化現象・社会的行為としてのまちづくり
- まちづくりと人類学的実践―毎日フィールドワークのすすめ