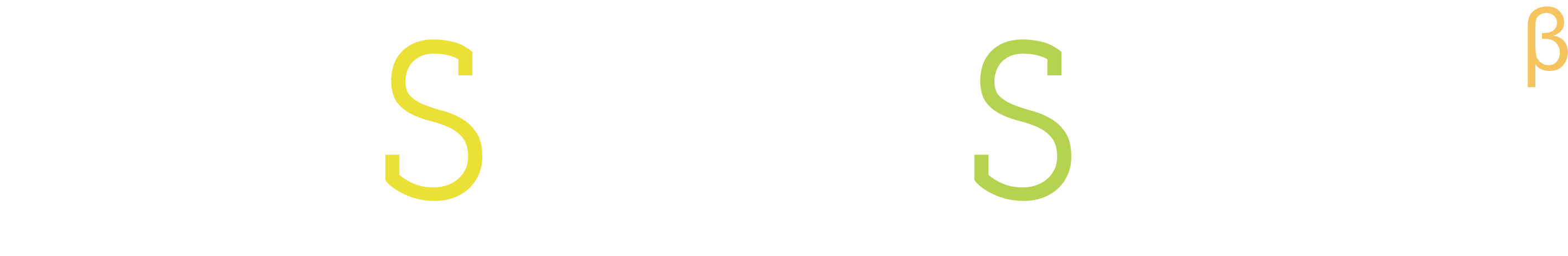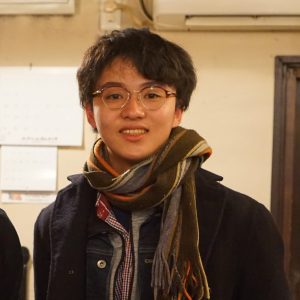本記事は「地域志向教育実習プログラムSUIJI-SLP(Six University Initiative Japan Indonesia-service learning program;スイジ)」をプログラムに参加した学生視点による「言語化」と「検証」に向けた全6記事における2記事目となります。前回の記事では、インドネシアと日本の地域でサービスラーニングを行う、SUIJI-SLPの概要の説明を行いました。
今回からSUIJI-SLPに参加した3人の学生と担当教員1人の計4人のインタビュー記事となります。初回は、インドネシアに留学されている佐々木周さんにインタビューします。最初は一, 二回生のSUIJI-SLPの体験が、その後の学生生活にどのような影響を与えたかを中心にお聞きします。
インドネシア留学中における研究
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]こんにちは!今日は高知大学の農学部の佐々木修さんにお話を聞きたいと思います。SUIJI-SLP に一年生の夏、春、二年生の夏、春の系 4 回参加されました。よろしくおねがいします![/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-sasaki-shu2.jpg” name=”佐々木” type=”r icon_yellow”]今日はよろしくね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]周さんは今、インドネシアのボゴール農業大学に留学されていますよね。インドネシアでは何を対象に研究しているんですか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-sasaki-shu2.jpg” name=”佐々木” type=”r icon_yellow”]今はインドネシアのソロという場所で、インドネシアのバティックについて調べてるんだ。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]バティック?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-sasaki-shu2.jpg” name=”佐々木” type=”r icon_yellow”]バティックというのは、ろうけつ染めという技法で作られているインドネシアの民族衣装の事だよ。ろうを置いた部分以外を染色することによって模様を作っているんだ。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]そうなんですね、バティックの具体的にどこに着目しているんですか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-sasaki-shu2.jpg” name=”佐々木” type=”r icon_yellow”]そのバティックの中でも天然の原料を用いた自然染料に着目して、だれがどこから自然染料をとってきているのか、自然染料はどのように作られているのかを調べているんだ。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]なるほど、理系のアプローチというよりは文系のアプローチで研究しているんですね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-sasaki-shu2.jpg” name=”佐々木” type=”r icon_yellow”]そうだね。質的な調査をしているよ。バティックはユネスコの無形文化遺産に登録されてはいるものの、自然染料を用いた物は激減していてね。文化財保護に研究を役立たせたいと考えて調査に取り組んでいるんだ。[/voice]英語が話せないから何もわからない
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]佐々木さんが SUIJI-SLP に参加されたきっかけは何だったんですか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-sasaki-shu2.jpg” name=”佐々木” type=”r icon_yellow”]日本の田舎に興味があったからかな。一年目の日本の活動で、トウモロコシを収穫したり、こんにゃく畑の草刈りをしたのは楽しかったな。あとは、農家さんにへのインタビューも印象に残ってる。インタビューをインドネシアの学生に英語で通訳するのが大変だったけどね。 [/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]農家さんに話を聞きながら、同時に通訳ですからね。大学の一回生にはハードだと思います。僕は SUIJI-SLP に三回生で初めて参加したのですが、三回生の僕でさえしんどいと感じたので。日本の田舎に興味を持っていたから SUIJI-SLP に参加したとおっしゃっていましたけど、国外の実習にはなぜ行かれたんですか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-sasaki-shu2.jpg” name=”佐々木” type=”r icon_yellow”]正直、雰囲気に流されていった。SUIJI-SLP は国内実習と海外実習がセットみたいになってるよね。だから、セットだし行くかみたいな(笑)[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]とりあえずだったんですね。たしかに、国内実習と海外実習がセットになっている事で国内に興味がある学生を海外に連れ出す事ができるのかもしれません。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-sasaki-shu2.jpg” name=”佐々木” type=”r icon_yellow”]一回生のころから何か目的をもって海外に行きたい人は少ないと思うから、そのような学生を連れ出せるのは SUIJI-SLP の特徴じゃないかな。 海外実習一年目の経験がSUIJI-SLP実習の中で一番衝撃的だった。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]どのあたりが衝撃だったんですか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-sasaki-shu2.jpg” name=”佐々木” type=”r icon_yellow”]英語がわからなかったから、何もわからなかった事だね。現地住民の話を通訳してもらってもわからないし、夜にミーティングを英語でやるんだけど、インドネシアの学生は英語ペラペラ、だけど自分は英語がわからないからミーティングにもついていけなかった。めちゃめちゃ悔しかったな。だから、ミーティングの前に日本語のメモを英語に直したりしたんだよね。[/voice]地域の要望と自分たちにできること
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]SUIJI-SLP はサービスラーニングプログラム、サービス(奉仕活動)とラーニング(学習活動)を組み合わせた教育プログラムですよね。サービスは地域のニーズを踏まえて行う必要があると思いますが、地域の方々からの要望はあったんですか? 佐々木さんは愛媛で実習を行っていたので、その時のエピソードがあれば教えてほしいのですが。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-sasaki-shu2.jpg” name=”佐々木” type=”r icon_yellow”]二年目の国内実習の時には、地域の方々から、移住希望者向けの体験住宅に人を呼ぶ方法を考えてほしい、という要望があったね。予算も用意してあるから、家具やインテリアとかも自由に作っていいよと言われてね。けど、それは 十日間の実習期間でやるには責任がありすぎるからできなかったな。結局、チームで相談した結果、家具などを作るのはあきらめて、別の提案を出そうという話になったんだ。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]予算まで用意されると責任が重くなりすぎますよね。用意していただいた予算に見合うだけの成果を出さなくてはならなくなりますから。そこまでのスキルと時間はないですからね。自分たちが責任を持てる範囲で活動を行う、というのは重要な視点だと思います。キャパオーバーな活動をすると中途半端に終わってしまって、逆に迷惑をかけることになりますから。最終的にどのような提案をしたのですか? [/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-sasaki-shu2.jpg” name=”佐々木” type=”r icon_yellow”]体験住宅の期間が最低で一年間というのは長すぎるから、短くした方がいいんじゃないかとか、一日ツアーをするとかを提案したね。けどそれらの案は、地域の方からは採用できないといわれてうまくいかなかったな。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]うまくいかなかったというのは?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-sasaki-shu2.jpg” name=”佐々木” type=”r icon_yellow”]地域の方は学生に意見を求めてるんだけど、最終的には自分たちにとって使える意見を出してほしいみたいだった。そしたらあなた達を受け入れた意味があるみたいな。 [/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-sasaki-shu2.jpg” name=”佐々木” type=”r icon_yellow”]それで、最終的には東京でブースを出した時使える紹介ビデオを作ったんだよね。実習先の地域では、人が温かい所をアピールポイントにしていたから、地域の人にこの地域の良いところはどこですかって尋ねながらビデオを作ったんだ。ビデオで温かさが伝わらないかなと思って。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]そのビデオは実際に使われたんですか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-sasaki-shu2.jpg” name=”佐々木” type=”r icon_yellow”]実際には、実習の最終発表で住民の皆さんに見てもらっただけ。そこは反省点かな。[/voice]SUIJI-SLP の良いところは?
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]最後に、佐々木さんが 思うSUIJI-SLP の特色とはなんでしょうか。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-sasaki-shu2.jpg” name=”佐々木” type=”r icon_yellow”]二つあって、一つは日本の田舎に興味がある学生の目を海外に向けさせるところ。俺は日本の田舎に興味があって、海外の田舎に目を向けさせられたから。もう一つは、他の国の学生と同じ目線で地域に入るところかな。SUIJI-SLP は一つの目的に向かってやるから、意見も激しくぶつかる。けど、そこで相手の価値観とかがわかるんだよね。 [/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]なるほど、学生の興味を広げられる点と意見がぶつかるからこそ価値観の違いが分かる所がSUIJI-SLPの良い所だいうことですね。今回はありがとうございました。[/voice]おわりに
農作業などの、実際に体験することが与える影響は大きいと感じました。また、最初は国内の田舎に興味を持っていて、海外へ目を向けるきっかけはUIJI-SLPが海外の実習がセットになってたからという点が興味深かったです。次はSUIJI-SLPが終わった後も定期的に地域と関わる、農学部四回生の矢野諭稔さんにインタビューしたいと思います。