ADVENT CALENDAR 2018の最終日!ついに最後となるわけですが、フィナーレとしてShare Study代表のとしちるが三度、記事を書かせていただきます。
[kanren2 postid=”1639″]Share Studyの立ち上げから2年強。当初からキーワードにしてきたのは「教養」。魅惑的に聞こえる、もしくは威圧的に捉えられるであろう「教養」ですが、こだわってきたのにはわけがあります。
僕が所属する筑波大学は「総合大学」や「教育大学」であることで知られていますが、一学生として所属する中では必ずしも学びを広げることと深めることが充実した環境であるとは思えませんでした。そうした環境に身を置く中で、素朴に自分自身が考えていた「違和感」をとある先生(学部はフランス文学、院は国際開発経済学)に話していたところ、「要するに“教養”が大事だと言いたいんだね。」ということばがきっかけとなって「教養」に力点に置くようになったというのが内実です。
その後、Share Studyの運営をはじめとして、学術分野に限らないさまざまな人と関わる中で、その交流を促し、学びを深められる関係を示すことばとしてやはり「教養」ということばは相応しいと考えるようになりました。
ですが、この記事では、Share Studyを運営する中で異なる立場の人がことばを交わす中でも、意味ある形で共通用語として機能しうるような概念を練り上げ、新たに言語化することを試みます。まだまだ考え中ですが、Share Studyに関わる皆様、ならびに興味を持つ方々にお読み頂けると幸いです!
ADVENT CALENDAR 2018―25日の投稿

12月1日から24日までクリスマスを待つまでに1日に1つカレンダーを空けるという風習に習って、記事を投稿するイベント、それがADVENT CALENDAR!
手垢がついた教養という概念
「教養」ということばには、何か「高尚なもの」を思い起こさせるような、何かそれを「身に着けたい」と思わせるものがあります。
「教養はLiberal artsとしての自由学芸であって、人は自由になるために教養を身に着けるのだ」
「教養はBildung、Cultureとして人格形成に必要なものだ」
さまざまな意味合いと響きを持って用いられる教養という用語について、暫定的に清水(2010)の「公共圏と私生活圏を統合する生活の能力」として受け入れたいという記事を1年前に書きました((今回の記事は、毎年書いていた「思想シリーズ」が年末間近まで書けなかったことから思想β 2018としてまとめています。が、昨年書いた思想2017γよりも縮小版…この記事で提唱する「視養」という概念はその響きと意味から「相対主義」と捉えられる可能性があると考えています。しかし、「なんでもあり」といったものに回収するのではなく、あくまで異なる価値観や論理を持った者同士で批判的にもコミュニケーションをする「可能性」を残すことは相対主義に必ずしもなるようには考えていません。科学哲学における科学的実在論が「メタ正当化」を行うように、「視養」に関してもメタ的に意味づけをする必要があると考えています。特にこうした議論は政治哲学的なものに接近するでしょう。本記事では、そこに至る真っ当な議論を展開できるだけの時間的余裕と実力が足りてないので、脚注3にて少しだけ言及する以外、ほとんど言及はしていません!これからも継続的に考えていきたいと思っています。))。
清水真木(2010)『これが「教養」だ』新潮新書
「公共圏と私生活圏を統合する生活の能力」とは、18世紀以降に近代社会が形作られていく中で「政治に参加する自分」や「生活のために労働する自分」「家庭に属する自分」などといったように生活が分断されていく中でも、「さまざまな事柄に対処する中でも“自分らしさ”を見つけて交通整理をしながら適宜判断して生きる」ことを指します。
今でもこの「生きてれば大変なこともあるけど、上手く交通整理をしながら“自分らしく”生きる」という教養の捉え方は有効だと思っています。ですが、「教養」ということばは「教養がないね」などといったように、今や「教養がないことは好ましくないこと」かのように用いられることがあります。
僕の専門はディスコース研究(談話分析・言説分析)と呼ばれるものです。ざっくり言うと、社会文化的なコミュニケーションを扱う学問分野です。この分野ではことばをはじめとした「やり取り」を対象に研究を行いますが、ことばは「やり取り」だけではなく、文法といった形式やことばの意味をも扱います。
「教養」は名詞であり、コミュニケーションを行う上では「具体的に何をどう指示するのか」といったことが不明瞭になってしまいます。つまり、どんなに「教養とは◯◯である」としても、教養ということばを個々の具体的なやり取りで表現される際には、「その場(今ここ)」での意味合いや解釈がもたらされてしまいます。 さらに、古くから歴史的に積み重ねられてきた概念でもあり、その意味合いは冒頭でも述べた通りさまざまです。
「教養としての〇〇学」といったタイトルが付く書籍を見る度、何か「教養というものが無批判に”良い”ものである」とイメージされ得てしまうように思えます((サイエンスコミュニケーションにおいては「欠陥モデル」と呼ばれるように、専門家が非専門家に対し啓蒙的に知識を押し付けてきたことを反省的に捉えてきた経緯がありました。学術的知識があるからといって、それを受け取る側がそのまま「価値あるもの」として受け取るわけではありません。学術的研究を学ぶこと、身につけることには大いに価値があると僕は捉えていますが、皆が皆、そのように「価値あるもの」として受け取ると考え、そう「受け取らないのはおかしい」とするのは、異なる立場や価値観を持つ他者の視点を自分の視点に押し付けようとするまなざしだと言っていいでしょう。
))。また、教養というものを突き詰めると一冊や二冊の本を読んだだけで理解できるようなものではありません。ハッキリ言って、哲学的な議論をある程度理解できないと「教養」というもののこれまでの議論や内実は分からないでしょう((仲正(2010;P27)は政治哲学者であるハンナ・アーレントの人間観や政治性についての紹介をしつつ、「もともと自由人としての「活動」としての嗜みとしての<humanititas>だったのが、大学で専門に入る前の知的な訓練としての<humanitas(教養)>へと意味がズレてくる」ことを指摘しています。<humanitas>は「自由人としての嗜み」といった意味を持ったものでしたが、近代社会が勃興していく中で啓蒙主義的な影響を受け、「ヒトに生まれつき備わっている本性」を賛美する理念として変形していきました。これがドイツのゲーテに代表されるような「教養小説(Bildungsroman)」として「人格形成(Bildung←build)」として、文学作品や哲学書をはじめとした理想的な「人間性」をテキスト読解を介して磨くという姿勢が強まるようになったのです。しかし、人間に備わる「普遍的な人間性」なるものを信じ、人文系の学問を修めることで人間性に「目覚める」といった類の言説には仲正(2010;P32)が言うように僕も批判的です。自由という概念には<liberty>と<freedom>がありますが、<liberty>が「解放=自由化」という意味合いに対して、<freedom>は「政治的(ポリス的)な」意味合いを持ち、理性的な言論活動を行う政治的空間があってはじめて人間は自由になるとアーレントは発想します。つまり、アーレントは言語を中心としたコミュニケーションを行い、相手の人格に精神的に働きかけるといった人と人との「間」を重視した思想を展開しました。))。
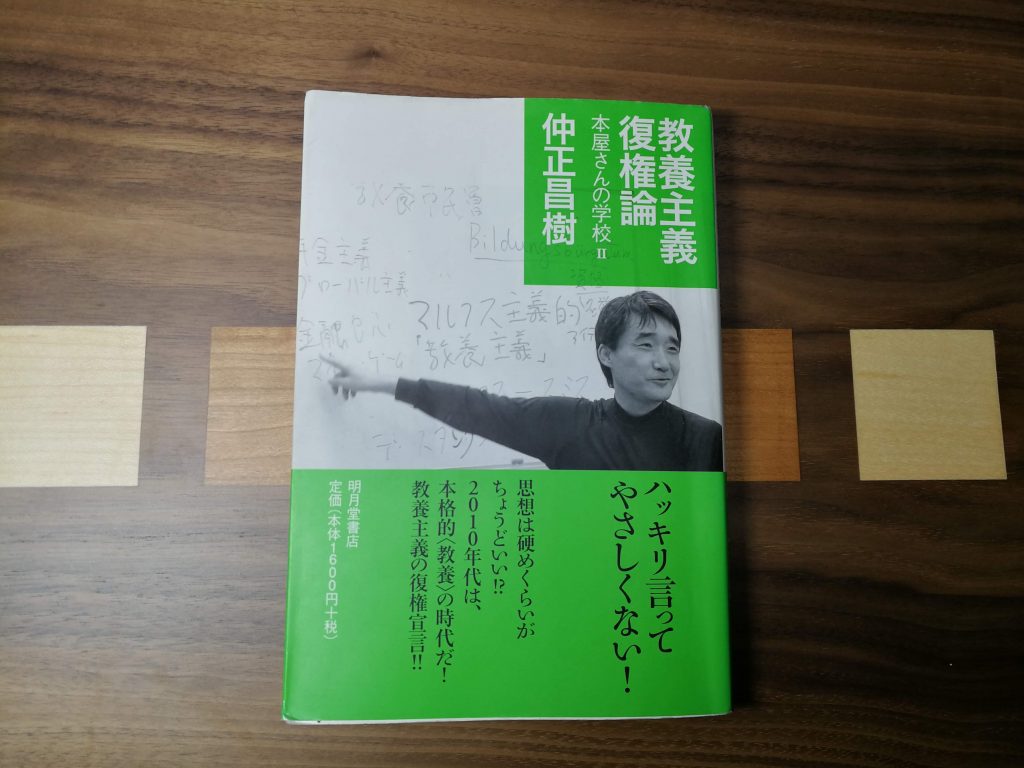
仲正昌樹(2010)『教養主義復権論 本屋さんの学校Ⅱ』明月堂書店((仲正さんは大量の哲学書籍を刊行する中で、学問の底上げを図っているかの如く執筆をされている哲学者の一人です。仲正昌樹(2011)『改訂版〈学問〉の取扱説明書』はまさに「ちょっと知識がついてふわっと語ってしまうような生意気な学生」レベルを対象に、「そんな単純ではない」ことを示唆してくれる良著です。))
これまでの教養という概念を批判的に捉えつつ、異なった現代的な意味として用いることができることばはないのか。そう考えていく中で、一つ新たに提案したいことばがあります。
それが「視養」という概念です。視養の説明に入る前に、簡単に僕が専門とするコミュニケーション論における重要概念を紹介しましょう。
コミュニケーション論における重要概念:オリゴ
コミュニケーション論、特に僕が学ぶ社会記号論系言語人類学において中心となるのは「視点」という概念です。「視点」と聞くと極一般的な用語のように聞こえますが、より専門的には「オリゴ」と言います((オリゴについてなど端的にまとめられているのが小山亘(2012)『コミュニケーション論のまなざし』です。言語学という形式を自然科学的に重んじる学問と、文化人類学という解釈的な学問の中間に位置する、言語人類学として展開する社会記号論系言語人類学の入門書と言えるでしょう。))。
具体例を簡単にあげます。「これ、明日までにやっておいてくれませんか?」ということばには、「これ(コソアドの指示)」「明日(時間)」といった何かしらに「焦点化」させることばがあります。このことばを山田くんが花子さんに言ったとしましょう。花子さんは「明日はお休みを頂いているのでできません…」と「応答」することで、山田くんのお願いを「お休み」に言及することでやんわりと断っていることが分かります((会話分析ではこのような「依頼 – 応答」といった関係を「隣接ペア」と呼びます。))。つまり、文の中だけでなく、会話の行き来にも「山田くん(依頼)→花子さん(拒否)」といったように、やり取りに焦点化されるポイントが浮き彫りだつ、それらすべてをオリゴと呼ぶわけです((会話のやり取りだけでなく、「コソアド:これ、それ、あれ、どこ」や「時制:過去、現在、未来」、さらには言及指示・社会指標するものすべてに介在するのが「オリゴ」です。山田「くん」や花子「さん」といった呼称も敬意や性を指示するものなので、社会指標性があり、「オリゴ」が転移する視点となりうるものというわけです。))。
コミュニケーションにおいては、「言われていること」だけではなく「為されていること」も指し示されます。この「言われていること」を言及指示、「為されていること」を社会指標とも呼びます。
オリゴというのはコミュニケーション論における一つの専門用語ですが、こうした専門用語を文化的意味範疇とも呼びます。もっと簡単に言えば、概念です。この文化的意味範疇もオリゴの変遷の中で変わっていくものだと捉えることができます。
このような視点に立つと、教養ということばの意味をもっと具体的なコミュニケーションの中で位置づけることができるようになります。
視養の定義
教養は、「自由学芸」や「人格形成」に、「自分らしく生きる力」といったように捉えることができます。しかし、「教養」はこれまでの歴史の中で意味づけされてきた、つまりオリゴの変遷とともに一定の意味付けがされてきた、文化的意味範疇(概念)でもあることが分かりました。
では、視養とは何か。端的に表せば、そのまま「視点を養う」ということです。教養のように単に「視養」と名詞として表現するよりも、「視養する」と表現できるように動的な概念であることを強調しています。もう少し、具体的に定義づけると下記のようになります。
自己と他者の相互的・重層的な関係性や社会文化的立ち位置による関心/利害を軸にしたそれぞれの視点を養うこと。
社会記号論系言語人類学の観点に立つと、個人や社会はコミュニケーション的産物であり、コミュニケーション的創成を行うこともできる両義的な存在です((「オリゴ」を中心に展開されるコミュニケーション論では、「個人主義(ミクロ)」的なコミュニケーション観や「社会文化的(マクロ)」なコンテクストを含むコミュニケーション観を含むもの、またそれらが相補的(補い合っていること)をもメタ的に捉える理論が展開されています。現代では「個人」が起点(独立変数)と捉えられる傾向にありますが、社会文化コミュニケーション論では「オリゴ」こそが起点(独立変数)として位置づけられ、コミュニケーションという事実が人間や心理、社会にとって根本的なものと捉えられるわけです。詳細な議論は、小山(2008, 2012)を参照ください。))((グローバル化が進んだ現代社会において、従来、「境界」や「領域」を持つものとして文化を定義することはかなり困難です。ソーシャルメディアを介して若者はなぜ情報発信を行うのか(なぜメディアに関わるのか)をリサーチクエスチョンに研究を行った集大成が高橋利恵(2015)『デジタルウィズダムの時代へ 若者とメディアのエンゲージメント』にまとめられています。高橋(2015)は分析を行う上での理論構築に「コミュニケーションの複雑性モデル」を提唱し、「個人・社会・文化」といった位相でさまざまな相互作用がそれぞれの「個人・社会・文化」を再帰的に構築しているとして論を展開します。その中で、Lull(2011)”Superculture for the Communication Age”では、6次元の文化圏から捉える「スーパーカルチャー(①普遍的な価値観②国際的な文化的資源③文明世界④ナショナルなイデオロギーと文化⑤リージョナルな文化⑥日常生活)」の概念を引き合いに、人々は「遠く(グローバル)」と「近く(ナショナルとローカル)」から文化的資源へアクセス、また流用する「文化プログラマー」として日常的に文化的プログラミングを行っていることを援用します。つまり、個人は日常生活の中でスーパーカルチャーを持ち、「ローカル」な文化的価値観や社会的実践を維持しつつ、また同時に個人間相互作用を通してスーパーカルチャーも影響を受けるというわけです。))。つまり、先に「個人」がいるのではなく、先に「オリゴ」を介した社会文化がある中で、私たちは存在していると捉えます。歴史的な存在として、「ある時」「ある場所」に生まれる人間は、否が応でも、その時・その場の「オリゴ」に巻き込まれてしまうわけです。それが「相互的・重層的な関係性や社会文化的立ち位置」であることを示しています。
一方、コミュニケーション的産物であるだけでなく、コミュニケーションを介して新たな社会文化を示していくこともできます。例えば、情報技術が発展した今、私たちは単に情報を受け取る受動的な存在なのではなく、自らも情報を積極的に発信する能動的な存在でもあります。会社を立ち上げ成金を目指したり、社会改善を願ったり、大学に在学する中で海外に飛び出てNGO・NPO活動に従事したり、海外インターンを行う中で就職をするといったこともあるでしょう。
情報技術の発展に伴って入り組んだ世界であることがわかった現代社会では、「個人化」が進んでいるとされています。「情報化」というよりも、「情報の消費化/個人化」が進んでいることを指摘する岡野(2016)は以下のように論を結んでいます。
[…]ではすべてがネオリベラリズム的な市場中心主義のせいかというと、それだけではない。資本主義の内であろうと外であろうと、私たちは個人として情報を処理しなければならない。しかしその情報とは、自分の効用を最大化するための道具となるような情報ばかりではない。他者との多様なネットワークから得られる情報であり、それは他者からつねに否定される可能性に開かれつつも、他者に投げかけ、また他者から投げかけられる情報なのである((中略した本文では次のように論がまとめられています。「本稿では、現代の社会を「情報化」という視点でとらえることの困難さから出発し、かわりに「情報の消費化」および「情報の個人化」という視点を提案した。「情報の消費化」については、見田による議論を手掛かりとして、一見「情報化」と見える事態が資本主義経済の拡大の結果であることを示した。次に、Beckらの個人化論を手掛かりとして、個人個人が確率的情報をゲーム理論におけるプレイヤーのごとく処理しなければならない事態を「情報の個人化」として描いた。著作権や個人情報の諸問題を扱うために、「情報化の進展が理由で…」というのでは答えが見えない。ではすべてがネオリベラリズム的な[…]」))。岡野一郎(2016)『消費化/個人化の観点による情報社会論の再検討―「情報化」から「情報の消費化/個人化」へ』社会情報学 第5巻2号, P49 -50
岡野(2016)の論を援用すれば、どんなに情報化が進んでも情報を処理する上で「個人」として情報を処理する必要があり、資本主義的な原理の中では関心/利害をもとに情報の取捨選択や判断がなされるが、必ずしも自分にとっての利益を得るためだけに情報を処理するのではなく、「他者に否定される可能性」に開かれていることが重要であるというわけです。
例えば、学術的な研究を進める上でも、会社をはじめとした組織に関わる上でも、所属する中で生まれる人間関係からそう簡単に逃れられるわけではありません。各学問分野が共有する課題や問題意識があり、各会社(経営者・従業員)や家庭・個人が持つ視点があります。そして、それぞれの価値観は当然、時にぶつかりあいます。
視点を養う「視養」とは、学術分野に限らず、あらゆる存在に宿るオリゴを見定め、判断し、対話的/批判的にコミュニケーションしていく力を指して用いる概念として提起したいと考えています((「視養」はあくまでも学習、理解、説明、対話、批判といった理性的、特に学術・批評的コミュニケーションにおいて役立つ概念であると考えています。「オリゴを見定め、判断」と書くように、さまざまな視点を内在化することには苦労を伴うためです。例えば、認識論的に強い実証主義的な考えを持つ者が解釈主義的な議論を理解するには、一定のアイデンティティのゆらぎを経験する必要が出てくるでしょう。他にも、「労働者が経営者の視点を理解すべきだ」といったように視養の概念を用いてしまうと、非対称的な関係性を持つ相手に、弱い立場を持つ者が強い立場の「視点」を学ばなければいけないといった類の議論も可能になってしまいます。「視養する」ということが単なる搾取にはならぬよう、どの視点を取るべきなのかを理性・知性・感性を活用することができる社会的立場や役割を持った人が価値判断していくのもまた重要かと思います。しかし、前者の認識論レベルで議論を展開できるのであれば、まずは一歩引いてそれぞれの「視点」を共有すること、つまり前提をメタ的に議論していくなどといったやり取りをし、学び合う関係になることは一定の意義があると考えています。その点において、視養することは意義ある行為となりえるはずです。))。
視養の機能
学術的なコミュニケーションを紡ぐ上での存在論・認識論・方法論を学び、考えるためのメタ的な視点を喚起するために「視養」ということばをまとめましょう。
野村(2017)は社会科学の考え方には「存在論:基礎づけ主義/反基礎づけ主義」や「認識論:実証主義/批判的実在論/解釈主義」があり、さらにその上で「リサーチ・デザイン」や「手法」があるとまとめています((認識論とは「どのように世の中を認識することができるのか」という問いに対して、抱く考え方のことを指します。野村(2017)によると、「私たちは「客観的」に事象の相互関係を(あるいは因果関係すらも)観察できる」とする立場を実証主義、「目に見えない構造を説明することに主眼を置くべき」とする立場を批判的実在論、「人々がどのように出来事を解釈しているか、解釈しよう(させよう)としているか」に迫る立場を解釈主義と説明しています。近代とともに20世紀の社会科学における中心的な位置を占めてきた実証主義に対する形で、解釈主義や批判的実在論といった認識論が台頭してきたという経緯があります。
))。社会科学における方法論とは「認識論+リサーチデザイン+手法」とまとめられます。Furlog and Marsh(2010)によれば特に認識論は「皮膚」のようなものであり、その場・その場で変えられるものではありません。
野村康(2017)『社会科学の考え方ー認識論、リサーチデザイン、手法』名古屋大学出版会
Furlog, P. and Marsh D.(2010)”A Skin Not a Sweater: Ontology and Epistemology in Political Science“, In D. Marsh and G. Stocker (eds.), Theory and Methods in Political Science, 3rd ed. Basingstoke: Palgare macmillan, pp. 184-211.
自然科学として研究を進める者にとっては、こうした社会科学の前提がわからないと「不確かな研究手法や学術システムとなっている」と思うかもしれません。また、社会科学を学ぶ人間やそれに準ずるような人でも、存在論や認識論の議論としてどのようなものがあるのかを知っていれば、異なる認識論を持つ人とのやり取りをする際に役立ちますし、なにより短期間で容易に認識論的立場を変えてしまうことの危うさにも気づくでしょう。
また、社会科学において特に解釈主義的な立場を取る人にとっては自然科学的な研究に懐疑の目を向けるかもしれません。自然科学において根本的な「科学とはなにか」と問う分野に科学哲学があります。科学哲学で議論されている主要な問題の1つは実在論/反実在論の問題です。実在論は自然科学的な研究において素朴な観察では捉えきれない世界は実在すると捉えますが、反実在論ではあれやこれやの手を使ってその対象が「実在する」とは言い切れず、科学的成果は社会的に構築されているものだと主張します。
「研究」というと一重に成果が積み重ねられているものだと捉える方もいるかもしれません。ですが、研究分野にもそれぞれ傾向として現れる前提となる価値観があり、当然、何をどのように研究するかについては得意不得意があります。前提の違いは視点の違い、文化的意味範疇の違いとしてコミュニケーション論としては説明することが可能です。
学術的探究を行う上でも、「専門家/非専門家(例えば、研究者/学生の関係)」といった異なる社会文化的立ち位置を持つ人とやり取りをするにしても、視点を養うこと、つまり「視養する」ことによって前提を浮き彫り立たせ、建設的な対話や議論をするきっかけになるのではないでしょうか((「専門家/非専門家」と言及したのは、サイエンスコミュニケーションや科学技術社会論をはじめとした分野を意識して言及しました。その内実に本記事では言及する余裕はありませんが、従来、「”サイエンス”コミュニケーション」と「”科学”技術社会論」と名がつくように、自然科学が牽引する取り組みであることが読み取れます。これまで人文社会科学では、自らの研究の意義や内容を伝達する取り組みが書籍(出版産業)や新聞・テレビ(マスメディア)を介してなされてきました。しかし、竹内洋(2004)『教養主義の没落 変わりゆくエリート学生文化』で指摘されているように、既に「教養主義」は社会環境の変化や出版産業の衰退によって没落していると言っていいでしょう。在野の哲学者として自ら文化装置『ゲンロン』を構築した哲学者・批評家である東浩紀も、会社を経営することの両立に苦戦を強いられていると言っていいでしょう。このような状況の中で、何を誰にどのように語るのかは人文社会科学においても、情報技術によってエンライトメントされ、さまざまな活動を行う読者との関係性をどのように構築するのかは、以前とした大きな論点だといいと考えています。Share Studyも、こうした文脈の中でどのように立ち位置を置くことができるのか探っている状態です。))。
おわりに
学問と言っても、その人が生まれ、育ち、培ってきた「視点」に影響を受けながら、知識・思考を磨き、個人は学問分野を選び、「ある一定の価値観や傾向」を持つ集団組織に属するようになります((独立系研究者や在野研究者もいますが、なにかしらの学問分野に準拠する限りはその分野の社会集団に属して研究することになります。))。
大きく言ってしまえば、「情報の消費化/個人化」が進んだ世界では自分の興味関心に合う人とのコミュニケーションを「選択」することが容易にできるようになりました。ですが、私たちは「オリゴ」を介して自己/他者や社会/文化を作っていきます。
Share Studyはそんな情報社会に抗うある種、反逆的なWebメディアです。こうして記事を書き、インターネット空間に発することは、「オリゴ」が転移し、いついかなる状況で誰が読むかも分からないことを意味します。
確かに社会構造(階級や資本主義 etc.)は大きく存在し、私たちの社会を覆い、文化を変容させていますが、それを、現状と異なるより“まし”な可能性へと変えていくこともできるわけです。もちろん、長い時間がかかって変わっていくものなのでしょう。
Share Study、その創始者である青山俊之こと、としちるはそんな「可能性」にかけてこのWebメディアを立ち上げ、ここまで運営してきました。
まだたかが2年ちょっとです。当初掲げた5年には及びません。しかし、Share Studyは2019年度を目安に第一期としてのケリをつけようと考えています。それはもちろん、より「可能性」にかけるための準備として助走をつけるためです。
2019年には新しい取り組みもいくつか動いていきます。それは5年後、10年後のための布石としてです。ケリはつけますが、まだまだここから!
実は、立ち上げ当初から長らく放置していたShare Studyのロゴを改めて作成致しました。それがこちら!

僕の専門として紹介した社会記号論系言語人類学では、C.S.パースという哲学者の議論が前提にある学問です。パースは三角項を用いたあらゆる物事を解釈・説明する哲学(記号論)を展開しています。例えば、言語を記号内容と捉えれば、記号表現として解釈する第三の視点があるといったようにです。

パース記号論における記号の三角項
こうしたパースの議論やさらに僕が学ぶ批判的談話研究における弁証法的アプローチでも、二項対立で捉えるのではなく第三の視点が絡む議論を展開しています。
ノーマン・フェアクラフ(2012)『ディスコースを分析する 社会研究のためのテクスト分析』くろしお出版
ルート・ヴォダック+ミヒャエル・マイヤー[編](2018)『批判的談話研究とは何か』三元社
Share Studyは、僕の認識から(どうしても)展開されているWebメディアになります。まだまだパースの哲学も言語人類学や批判的談話研究も学びを進めている最中です。長く助走を取るのは、自分自身がしっかりと研究に打ち込み、鍛錬を積む時間を確保するため。
ですが、今できる限りで少しでも「可能性」に向けた議論を積み重ねるために一足を踏み出していきます。来年のShare Studyにもご期待くださーい!ではではHappy Christmas&良いお年を~!



