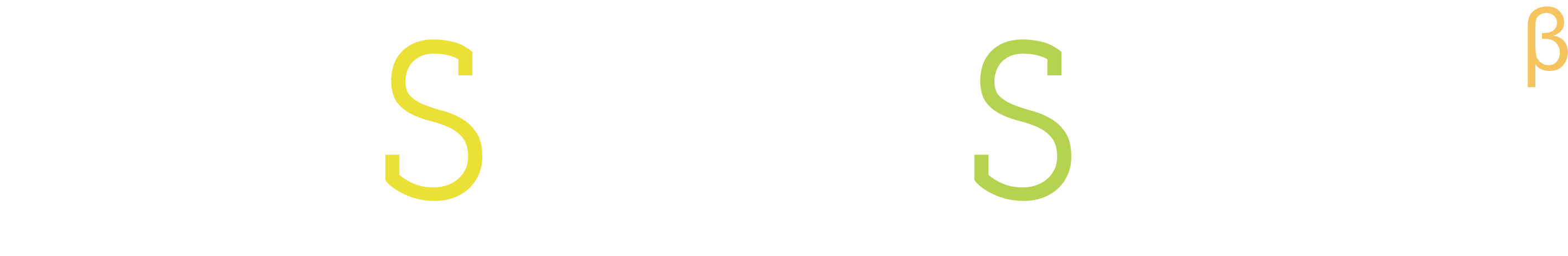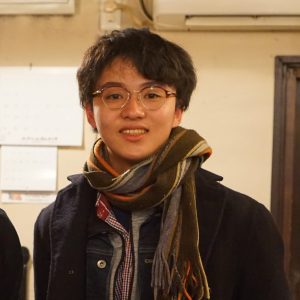前回までは、SUIJI-SLPに参加した学生にインタビューしてきました。今回はSUIJI-SLPの高知エリア担当の増田和也先生にインタビューします。プログラムを5年間続けてきた中で、SUIJI-SLPがどのように変化してきたのか。また、インドネシアと日本の大学の地域貢献事情の違いについてお聞きします。
研究分野:環境人類学
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]今回はSUIJI-SLPの高知サイトの担当教員の増田和也さんにお話しを聞きたいと思ます。よろしくお願いします。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]よろしく。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]まず、最初に先生の研究についてお聞きしたいと思います。先生のご専門は環境人類学という事ですが、どのような学問分野なのでしょうか?少し聞きなじみがないのですが。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]環境人類学は、人間と環境の関わりが、文化・社会・自然生態の諸条件が関連しあいながら、どのように築き上げられ、変容してきたかを見ていこうという学問分野だね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]文化人類学はよく聞くのですが、違いはどのようなところにあるのでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]文化人類学は文化事象に注目して、それぞれの地域社会の特徴を浮き彫りにしていくのに対して、環境人類学では、自然や資源の利用のように、より生態や環境に関連したトピックに注目していく。そこに、自然生態的要因だけでなく、いかに文化や社会制度、政治・経済といった側面が絡んでいるのかを明らかにしていく、といった感じかな。[/voice]フィールドワークの醍醐味
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]先生の具体的な研究内容はどのようなものなんですか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]インドネシアのスマトラ島中部の森に暮らしてきた人たちの土地利用をめぐる規範の変化について研究してきた。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]もう少し詳しく教えてください。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]まず、僕がフィールドワークをした村では焼畑と森での狩猟採取をやっていたんだけど、1990年代末からプランテーション作物のアブラヤシが入ってきて土地利用のルールが変化したんだ。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]焼畑とプランテーションは土地利用の仕方が大きく異なりますよね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]そうだね、焼き畑は1、2年耕作して、その後は他の場所に移動していくけど、アブラヤシは多年生の植物だから同じ土地での耕作が続くね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]なるほど、いろいろな場所に移動していく栽培方法から同じ場所で連続して育てる栽培方法に代わっていったんですね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]そうなると、土地を実質的に私有化するような動きが出てくる。それまでの調査地では、焼畑は共有地内で慣習にしたがって拓かれてきたから、こうした動きのなかで、村びとの間で土地をめぐる確執が起こるんだ。村びとたちは、共有地内の土地をいかに自分のものにするかということで、過去に自分や先祖が焼畑を拓いた事実を引き合いに出したり、いろいろな理屈をこねたりする。こうして、共有地をめぐる慣習が解体されるプロセスを追っていった。ただし、ここにはもう一つの側面があって、村びと同士における土地問題に加えて、村びとたちは国家や農園企業との間でも土地問題を抱えていて、それにも関連しながら村の慣習が変容してきたんだ。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]国家や農園企業との土地問題は、どのように慣習に関わっているんですか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]国家は法律を後ろ盾にして、割と一方的に土地を奪おうとしているんだけど、そのようなときに村びとたちは、昔からの共有地の慣習を根拠にして自分たちの土地の権利の正統性を示しながら、国家や企業と争うんだ。つまり、対外的な文脈では共有地をめぐる慣習とその正統性が強調されているけれども、村の内部では土地の共有性が解体されているんだよね。こうやって、今を生きる村びとたちの暮らしの一面を描き出したつもりだよ。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]土地利用の慣習には二面性があるんですね。ところで、どうして、そのテーマを選ばれたのですか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]最初は別のテーマで調べていこうと思っていた。けれども、村に滞在して、村の様子を観察したり、村びとに話を聞いたりするなかで、当時の村の暮らしのなかで一番ホットなテーマがアブラヤシ栽培導入に由来する土地問題だと感じたんだ。そして、村びとが時どき話してくれる焼畑に関する思い出話が、土地をめぐる今日の問題にも結びついていると直感した。過去と現在をつなぎながら村の暮らしを描き出せると思い、現地に入ってからテーマを変えた。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]それでは、当初の計画どおりではないのですね?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]そのとおり。フィールドワークの面白さは、そういうところにあると思う。いろいろな思いをもって現場に出て行くけれど、それが良い意味で裏切られる。僕らの思い込みもあるし、地域社会だって常に変化している。だから、その場その場で、テーマや方法論をたえず修正していく。当初には想像もしなかった事象やテーマに出会った時の興奮、というか高揚感。そして、それを実証していくこと。それが、フィールドワークの醍醐味だと思う。[/voice]ゴミ箱という名のゴミを作った
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]SUIJI-SLPの話に移りたいと思います。増田先生はSUIJI-SLPには初年度から関わられていますよね、そこから6年SUIJI-SLPを行っているわけですが、初期のころからの変化はあるんですか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]プログラムの目標というか、ねらいかな。当初、このプログラムが構想された時には、地域が直面している課題を知って、地域のためにその課題の解決に向けて、何かをするということだった。だから、その最終目標である、「地域のために何かをする」っていう事を意識しすぎたんだよね。本来、地域での実践活動は段階を踏んで行うものなのだけれど。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]それは、先生だけではなくて、学生もですか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]そうだね、教員がそういう目的を言っているから、学生も意図を組んで無理に何かをしてしまのかもしれない。「地域貢献」という言葉に惹かれて参加する学生もいるし。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]無理してやったというのは、具体的にどのようなことをしたんですか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]初年度の国内実習ではゴミ拾いと草刈りだね。海外実習ではゴミ箱を作った。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]無理をしたとは、どのような意味なんでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]現地に滞在する約十日間でできることは限られている。そうした時に、インドネシアの村で、まず学生たちの目に強烈に映ったのが、そこらに放置されたままの山積みのゴミ。村では、ゴミをまとまったところに捨てる習慣がない。もともとは、バナナの葉っぱなどを包み紙や皿として使っていたから、ついついその場で捨ててしまう。バナナの葉は分解されるから、とくに問題にならなかった。そのようなところにゴミ箱を作っても、誰も使わない。そもそもゴミ箱に集まったゴミを回収する人もシステムもない。だから、結局は、ゴミ箱を作っても意味がなかった。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]根本的な問題はゴミ箱がない事ではない、という事に気づけなかったんですね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]結局、ゴミ箱という名のゴミを作った、という感じになっちゃったね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]十日間で何かをしろと言われても、そうなっちゃうと僕は思いますね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]他にも、国内実習での「こうしたらよいのでは」という提案も、「その提案を実行する人がいないのが問題だからやめてほしい」と間接的に言われたこともある。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]無責任に言わないで欲しいということですかね。他の地域だと「何でもいいから言ってほしい」というところもありました。そこはコミュニケーションの問題だと思います。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]だから2年目、3年目からは、最終的には地域のためを目指すのだけど、まずのこと地域を知るために、一つのテーマで掘り下げながら、地域のことを理解することから始めよう、と思うようになった。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]まず、地域を知ろうとすること。それが大事ですよね。[/voice]インドネシアの地域貢献
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]SUIJI-SLPはインドネシアの大学と合同で行っていますが、向こうの大学との地域とのかかわり方の違いはあるんでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]インドネシアでは日本以上に地域貢献が進んでいて、50〜60年の歴史がある。大学によっては、全学生が2ヶ月間近く、農山漁村に住み込みながら、地域貢献活動をすることになっている。そもそも、SUIJI-SLPの構想は、インドネシアの大学の地域貢献実習をヒントに生まれているんだ。向こうでは専門知識を持った学生が地域に出かけて指導を行っていて、それが成果を上げている。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]50〜60年前からやられているんですね。日本より大学と地域の連携が進んでいるのか。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]そういう事情もあって、まだ専門性のない1・2回生を地域に送るのはとんでもない、という雰囲気がある。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]専門的な知識を持って地域に出るという事と、このSUIJI-SLPの目的違う気がしますが。あくまでSUIJI-SLPは教育プログラムですし。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]インドネシアの地域実習は、政府による村落開発の一環に組み込まれていた、ともいえる。だから、いまだにインドネシアの大学からの参加者は上回生が多い。そこでかみ合っていないかな。[/voice]手ごたえはない
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]教育は難しい、といつも思っている。とくにそれぞれの学生に各自のテーマを見つけさせて、それぞれのフィールドワークをサポートするというのは、もう大変。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]自分のテーマを見つけるというのは本当に難しかったです。けど、短い期間でしたが、そのようなことを経験できたのは良かったと思います。自分では成長できたかなと思っています。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]正直、僕自身には、この実習で学生が成長した、という手ごたえはないんだよね。一つのサイトに15人ほどの学生がいて、実習期間も短いなかで、ひとり一人の話をじっくり聞きながらアドバイスをする、というのは、正直いって、かなり厳しい。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]手ごたえがない、というのは意外でした。僕の周りだとSUIJI-SLPの体験から変わった学生を見るので。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]良い意味で変わってくれた学生はいるんだけど、それは別に僕が何かしたわけじゃないと思うんだよね。僕自身は、学生が現場に出て行く機会や場所をアレンジしたり、バックアップしたりする程度にしか思っていないな。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]うーん、そうなんですね。フィールドワークを行うにおいて場所が提供されるというのは、1, 2年生にとってはとても助かるのではないでしょうか。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]現場に出て、個人的なテーマを自分で見つけていくことが面白いよ、と伝えられたらいいなと思っているけど、やっぱり難しい。勘がいい学生もいるけど、うまくいかない学生もいるし、実際、そのような学生の方が多い。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]たしかに、言われたことを勉強するというのに慣れていると大変ですね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]とはいえ、去年あたりから、自ら地域でやりたいこと見つけて継続している学生が出てきているのは、うれしいな。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]後輩たちの成長が楽しみです。今日はありがとうございました。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/interview-icon-suiji-m.jpg” name=”増田” type=”r icon_yellow”]こちらこそありがとう。[/voice]おわりに
実習で課題解決を急ぐあまり、地域にごみ箱という名のごみをつくってしまったという話が印象的でした。インドネシアの大学では地域との連携が日本以上に進んでいる事も驚きでした。次回、最終記事となる第6記事目は、SUIJI-SLPを一学生目線からの「言語化」と「検証」として振り返り、「大学」「地域」「学生」の関わりを考察したものです。