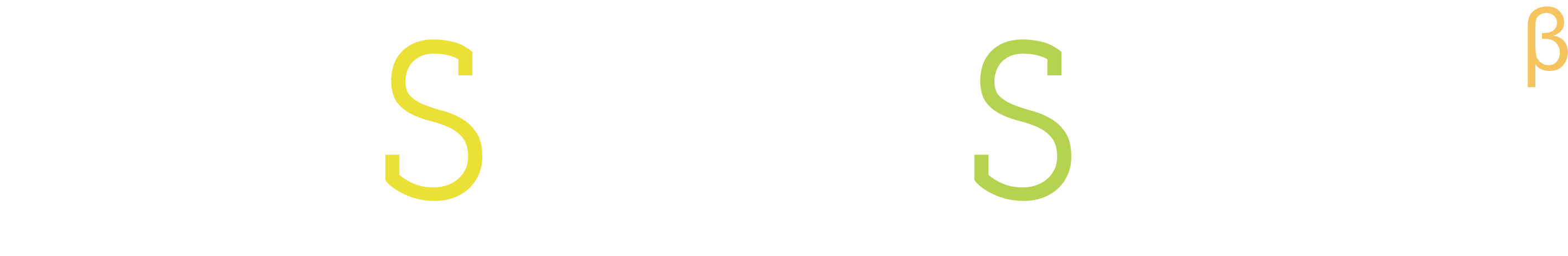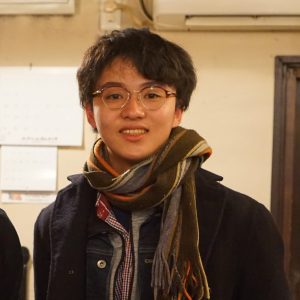本記事は「地域志向教育実習プログラムSUIJI-SLP(Six University Initiative Japan Indonesia-service learning program;スイジ)」をプログラムに参加した学生視点による「言語化」と「検証」に向けた全6記事における3記事目となります。前回の記事では、インドネシアに留学されている佐々木周さんに、1, 2回生のSUIJI-SLPの体験を通してどのような影響を与えたのかについてインタビューを行いました。
SUIJI-SLPを通じて、日本の地域から海外へ目を向けていく話が印象的でした。今回はSUIJI-SLPを通じて学ぶ事の楽しさを知ったという矢野諭稔さんにインタビューします。
計4回、SUIJI-SLへの参加
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]今回はSUIJI-SLPに1年の夏・春、2年の夏・春の 4回、すべて参加した高知大学農芸化学科、四回生の矢野君にインタビューします。SUIJI-SLPのベーシックコース、アドバンスコースと二年間、計4回参加する学生は4分の1より少ないです。貴重な経験談を聞けると思います。今日はよろしく! [/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-yano.jpg” name=”矢野” type=”r icon_red”]よろしく![/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]矢野君は国内の実習場所だった愛媛にも何回も授業外でも通っていて精力的だと思っている。高知からだと、車で3時間もかかって大変だなと思う。 [/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-yano.jpg” name=”矢野” type=”r icon_red”]毎回、行くたびに勉強になるし、地域の人に会いたくなるから、関係が続いているのだと思う。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]勉強になるというのは具体的には?[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-yano.jpg” name=”矢野” type=”r icon_red”]行くたびに地域の違う側面が見れるんだよね。こういうものがあったのかとか、自分たちの地域をこういう風に考えている人がいたのかとか。 [/voice]海外ボランティアに興味があった
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]矢野さんが SUIJI-SLP に参加した理由は何だったの? [/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-yano.jpg” name=”矢野” type=”r icon_red”]高校卒業してから海外に興味が出て、インドネシアに行って何かできるんだったら SUIJI-SLP に参加しようかなと。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]けど、SUIJI-SLP は春の海外実習に参加するには、夏の国内実習に参加しないといけないわけだよね。そこらへんはどうだったの? [/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-yano.jpg” name=”矢野” type=”r icon_red”]国内実習をこなさないといけないみたいな感じ(笑) [/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]そこまで、国内実習に思い入れはなかったんだね。何回も愛媛の実習地に通っているから、最初から国内の地域、田舎に興味があったのかなと思ってた。僕の感覚だと、日本の田舎に興味があるから SUIJI-SLP に参加する人が多いイメージがあるんだけど。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-yano.jpg” name=”矢野” type=”r icon_red”]そんなことないよ。どちらかというと、海外に行くために SUIJI-SLP に参加する人が多いと思うよ。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]異文化交流をしたいと感じている学生が参加している感じかな。けど、今年の高知大学の参加者は地域に興味ある人が多かったような気がする。世代、大学によって異なるのかもね。[/voice]SUIJI-SLP 負のスパイラル
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]その「行かなきゃいけなかった」一年目の国内はどうだったの? [/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-yano.jpg” name=”矢野” type=”r icon_red”]まじめにはやったよ。サービスラーニングだから地域が学生に何を求めているんだろうと考えてたんだけど、答えがまったくわからなくてしんどかったね。まじめな学生ほど陥ってしまう SUIJI-SLP の負のスパイラルになっていたと思う。「なんでこのプログラムをやっているんだろう」って考えすぎて、何をすれば良いのかがわからなくなる、負のスパイラル。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]負のスパイラルか。まじめな学生ほど、考えすぎてしまって動けなくなることはあるよね。まじめな学生ほど、というのはわかる気がする。 [/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-yano.jpg” name=”矢野” type=”r icon_red”]僕が参加した、実習地の学生間では語り継がれているけどね。地域の求める事をしないといけない、という思いがあって、その結果、地域が何を求めているのか考えすぎてしまう。そして、何をしたらいいのか、わからなくなってしまう。それが負のスパイラル。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]なるほどね、地域に何ができるのかを考えるのはある程度大事だけど思う。だけど自分たちだけで考えてもわからなくて、地域の方々とコミュニケーションをとるしかないよね。今年の夏に俺が SUIJI-SLP に参加したときは、考えすぎて動けなくならないように 、十日では何もできない、とある程度割り切ったけど。SUIJI-SLP の活動の自由度が高い所が悪い側面として出ているのかもね。 [/voice]知識が足りないと気づいた?
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-yano.jpg” name=”矢野” type=”r icon_red”]4回目の国外の実習で一番成長したと思うんだよね。今が100だとすると、夏0→春5→夏10→春70みたいな感じで。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]それは、なんでなの?きっかけとかあったから? [/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-yano.jpg” name=”矢野” type=”r icon_red”]1年目の国外の実習の最終日の3日前に、アドバンスドコースの先輩から地域を掘り下げる方法を教えてもらったんだよね。方法は本当に単純なんだけど、フィールドで見つけた「なんでだろう?」という疑問を尋ねていくだけなんだよね。その時に、これが学ぶってことかなって思ったかな。でも、掘り下げかけて終わった感じ。 [/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]その経験が二年目の国内実習には生かされたの? [/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-yano.jpg” name=”矢野” type=”r icon_red”]それで、二年目の国内はとにかく地域の人に話を聞こうとした。その結果、「十日間しか来ない学生に何も期待していない、何かを作るのではなく、この地域を見て何を感じたかを言ってほしい」という一年目には聞けなかった学生への思いも聞くことができたかな。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]さっき言った負のスパイラルの回答が得られたんだね。けど、その回答も地域における一人の意見という所があるから難しいよね。それでもまだ、成長度合いとしては 10/100 なわけだよね。何が起きたの? [/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-yano.jpg” name=”矢野” type=”r icon_red”]国内実習の時に井戸の写真を撮ってたんだよね、その時はただ凄いと思っただけなんだけど。そしたら、インドネシアでも井戸を見つけて。ここからどうやって掘り下げようかと考えて先生の相談したときに、深めるために知識が必要だと、ようやく気づいたんだよね。それで、知識を得るために勉強をしないといけないと思ったんだよね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]疑問を持つという事と、知識が必要という事が大事と認識したわけだ。勉強する内発的な動機はとても大事だよね。[/voice]SUIJI-SLP をどうとらえるか?
[voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]SUIJI-SLP を終えて、今はどう捉えている? [/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-yano.jpg” name=”矢野” type=”r icon_red”]方法論を持たないで地域に行くのは酷だなと感じる。俺は地域に入りながら先生に教えてもらえたからよかったけど。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]確かに、事前授業はあるけど十分だとは言えないと思う。課題解決をするにしても、地域の事を知るにしても振り回せる武器は必要だよね。ただ、放り込まれるだけで勝手に学生は成長しないしね。 [/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-yano.jpg” name=”矢野” type=”r icon_red”]いい所は SUIJI-SLP を経験して、今まで受け身だった勉強が受け身じゃなくなった。いろんなことを経験して、地域の人、先生、海外の学生、後輩と出会って、楽しみながら興味を深められるようになった。もう、勉強じゃなくなったね。[/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2017/12/39_kochi_kobayashi.jpg” name=”小林” type=”l”]何かに出会い面白いなあと思うと勉強したくなるよね。矢野が言った通り、勉強という感覚がしない。これが、大学での学びなのかもね。 [/voice] [voice icon=”https://share-study.net/wp-content/uploads/2019/04/icon-yano.jpg” name=”矢野” type=”r icon_red”]やっとそれができるようになった。[/voice]おわりに
地域が何を求めているかを考える事は重要ですが、一方で考えすぎるあまり身動きが取れなくなってしまう事は課題だと思いました。フィールドでの発見したことを深めていく過程を通して、学ぶことが楽しくなっていったという矢野君の言葉はフィールドワークの楽しさを表しているのではないでしょうか。次は、一回生の時にSUIJI-SLPの国内実習に参加し、実習地で活動する学生団体を立ち上げた岡本さんにインタビューしたいと思います。