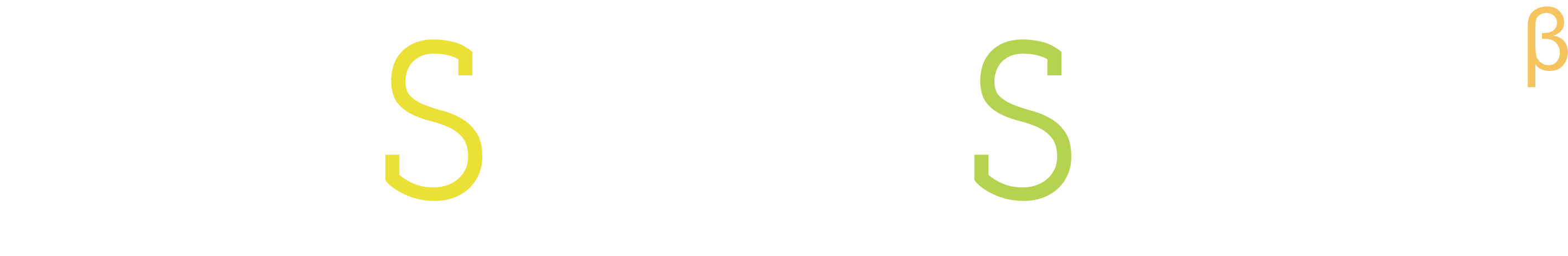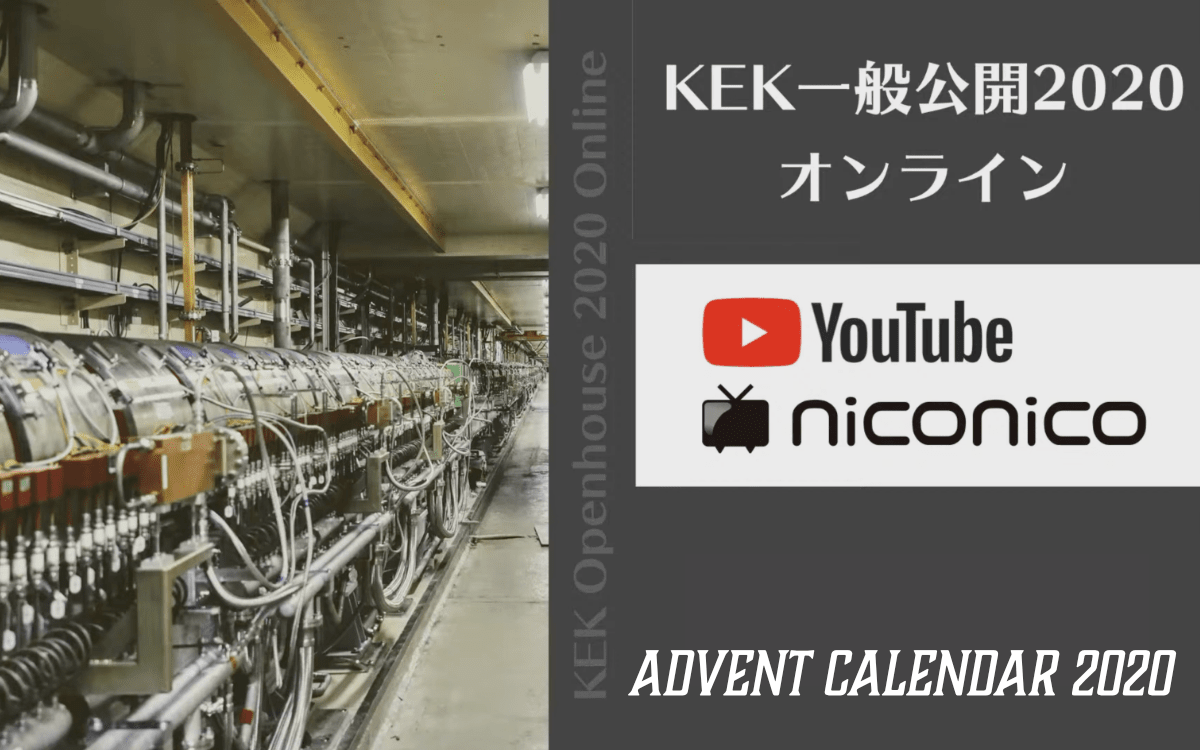おはようございます!こんにちは!こんばんは!Share StudyのADVENT CALENDAR 17日目の投稿。科学コミュニケータのしょーたです。
新型コロナウイルスの感染拡大の観点から、年中行事として開催していた多くの科学イベントが中止や延期もしくはオンライン化を余儀なくされました。「ピンチはチャンス」というと不謹慎に聞こえるかもしれませんが、今年は《いまできること》をうまく見つけて、新しいことにチャレンジするいい機会だなとポジティブに考えています。
この記事では、今年一番ハードなチャレンジであった「KEK(高エネルギー加速器研究機構)一般公開2020オンライン」の裏側について書いてみました😊

高橋しょーた
ADVENT CALENDAR 2020―17日の投稿

12月1日から24日までクリスマスを待つまでに1日に1つカレンダーを空けるという風習に習って、記事を投稿するイベント、それがADVENT CALENDAR!
前哨戦:勝手に科学技術週間2020
4月18日は「発明の日」。毎年、この日を含む1週間は「科学技術週間」と呼ばれています。おそらく、ほとんど知られていないと思います。つくば市にある多くの研究機関はこの時期に様々な科学イベントを開催します。一般公開をここに設定する研究機関もあります。
3月末ころは、まだ科学技術週間を開催する雰囲気がありましたが、緊急事態宣言によって一変。KEKもそうですが、ほとんどの機関の常設展示や見学ツアーなども臨時閉館となり、科学技術週間に関連したイベントは軒並み中止になってしまいました。
このまま科学イベントがなくなってしまうのもなんだか寂しかったので、つくばの研究広報仲間に声をかけて、有志でライブ配信イベントを開催することにしました。配信会場はどこにしようか?up Tsukubaの江本さんに聞いてみたら場所を提供してくれ、出演も快諾してくれました。イベント名は「勝手につくば大使」という大先輩にインスパイアされ「勝手に科学技術週間2020」としました。実際にどんなことをしたかは江本さんのnoteに書いてあるので、ぜひ読んでみてください!
note: 勝手に科学技術週間 でやったこと(主に動画配信まとめ)
このイベント、有志で《勝手に》開催したのですが、配信機材のセットアップやZoomを使ったリモートセッション、など次に紹介するKEK一般公開2020オンラインに向けたプロトタイプとなっています。特に、ここでBlackmagic DesignのATEM MiniのスイッチャーやZoomを使ってみたり、音声でちょっと失敗してしまった経験は、機材選定やコンテンツ考案にまるまる取り込んでいます。後付な感じ強めですが、僕の中では、一般公開はこのときから始まっていました。
KEK一般公開2020オンライン
巨大な実験装置「加速器」を使って、宇宙の謎・物質の構造・生命のしくみを研究しているKEK。一般公開は毎年9月に開催しています。 普段見ることのできない施設や装置の見学をはじめ、第一線で活躍する研究者の講演、こども向け体験コーナーなど、様々な企画を楽しむことができます。平たく言えば、KEKの総力をかけたお祭りです。
今年は、新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、オンラインで開催しました。研究施設の紹介動画を新規に撮り下ろして公開したり、研究者とのライブセッションをYouTube Liveとニコニコ生放送を使ってお届けしました。
一般公開の準備はいつから?
外からは見えない情報ですが、今年の一般公開に向けた準備は年が明けたころからぼちぼち開始していました。これは例年より3ヶ月くらい早め。そこに新型コロナがやってきました。
開催の是非に関しても、中止にしてもしかたないのでは?秋ころには例年通り現地で開催できるのでは?オンライン開催する場合は外注すれば?と様々な意見があり、実際に開催方針を決定したのは5月末。オンライン配信をすることになりました。
まだ緊急事態宣言も出ていたので、外注するという選択肢は事実上なく、すべて自分たちで内製することにしました。また県外からゲストを呼ぶことも難しい状況だったので「地域とのつながり」も裏テーマに設定しゲスト選定をしました。
オンライン配信に関しては、過去にニコニコ生放送を実施したり、上に書いた「勝手に科学技術週間2020」に挑戦したりした経験があったので、なんとなく大丈夫だろうと考えていました。でも、実際にやってみたら・・・やはりものすごく大変でした。
機材の購入は間に合うのか!?
オンライン配信をするための機材を十分に持っていなかったので、追加する必要がありました。配信の要となるスイッチャーは、勝手に科学技術週間で使った機器の上位機種であるATEM Mini Proを使うことにしたのですが、5月の時点でなんと納期が3ヶ月待ち!すぐに発注したものの「本当に納品されるのだろうか?」という大きな不安をギリギリまで抱えることになりました。
納品されなかった場合の代替手段としてHDMIキャプチャーボードなども考えたのですが、こちらも時すでに遅し。オンライン会議の需要増加に伴い、オススメ機種はすべて欠品状態でした。
代理店の担当者にも何回か納品時期の確認のメールを送ったりして、首をなが〜くして待っていたスイッチャーは8月の最後の週に納品。購入者を対象にしたBlackmagic Design主催の操作解説ウェビナーにも参加して、気になってたことを質問したりして、なんとかリハーサルにも間に合うようにセットアップしました。ほんとギリギリ!
胃がキリキリしつづけた動画編集漬けの夏
オンライン配信中に研究施設の様子を中継する案もありましたが、人材不足から配信トラブルが起きた際のリカバリが難しそうだったので断念。その代わりに研究紹介動画を新しく15本ほど作成しました。対象は科学のライトファン、長さが3〜5分を基本コンセプトとした動画シリーズとし、製作時のやる気を高めるために「Quanum Insiders」と名付けました。
たった3〜5分の動画ですが、撮影には3時間ほどかかりました。4日で6本撮影した週は本当にクタクタ。編集にも5倍以上の時間がかかっていたと思います(実はまだ公開できていない動画もある)。
この時期は割とテンション高めにして乗り切りました。が、裏では百草丸、バファリンと友だちでした。毎日投稿する人気YouTuberのすごさを実感。ほんとすごい。
おわりに
振り返るともっとあるのですが、細かい話なのでこの辺りで強引におしまいにします。
おかげさまで、YouTube Liveとニコニコ生放送合わせて約2万人の方にご覧いただき、YouTubeチャンネルの登録者も年始から3倍以上になりました(もともと1000人もいなかったためでもある)。大成功です🎉
オンライン配信・・・口に出して提案するのは簡単ですが、想像の3倍以上の時間とエフォートが必要であるなと実感しました。今回は、機材設定のテストにも多くの時間を取られていて、振り返るとまるっと1週間持ってかれていました。ただし、機材は人間と違って、テストでできないところが、当日うまくできるはずがないので、不安要素を徹底的に潰しておいてよかったと思っています。ある程度のノウハウも得たので、来年はもっとコンテンツ作成に時間を当てられそうです。
こんなにもキリキリでギリギリなことはなるべく回避したいですが、今後も、研究所の魅力を届けるコンテンツを発信していくので、ぜひお楽しみに!